タイトル:白金の鎖、レム睡眠の彼方へ
序章:南船場の不眠症
大阪、南船場。御堂筋から少し入った、石畳がモダンな雰囲気を醸し出す一角に、相田翔太が経営する「ブランドクラブ」は静かに佇んでいた。彼の店は、単に高価な品を右から左へ流す場所ではない。一つひとつのジュエリーや時計に秘められた来歴を紐解き、その価値を理解する次の所有者へと橋渡しする、いわば物語の継承を担う場所だった。翔太自身、三十代半ばにしては落ち着きすぎていると評されることが多く、その物腰の柔らかさと、品物に向ける真摯な眼差しが、多くの顧客から信頼を得ていた。
しかし、そんな彼をここ数ヶ月、深刻な問題が蝕んでいた。不眠だ。夜、ベッドに入っても意識は冴えわたり、羊を数えるどころか、店にある在庫の微細な傷の数まで思い出してしまう始末。ようやく訪れる浅い眠りも、脈絡のない悪夢に寸断され、朝には鉛のような倦怠感だけが残る。心療内 клиникで処方された睡眠薬も、最初は効いたが、すぐに耐性ができたのか、気休めにしかならなくなっていた。
その日も、翔太は寝不足による鈍い頭痛をこめかみに感じながら、ショーケースを磨いていた。彼の視線が、一点に吸い寄せられる。それは、先日、古くからの顧客である老婦人から買い取ったばかりのネックレスだった。
「F4003 SEIKO Pt850 W6面喜平 40cm 41.4G 5.49mm ユニセックスネックレス メーカー&造幣局マーク」
プラチナ850の、重厚でありながら品格のある白い輝き。ダブルで編まれた六面カットの喜平チェーンは、どの角度から光を受けても滑らかで連続的な反射を生み出し、まるで液体金属のようだ。手に取ると、41.4グラムという質量が心地よく掌に沈む。冷たく、滑らかな感触。それは単なる貴金属の塊ではなく、長い年月を経てきたものだけが持つ、一種のオーラを放っていた。セイコーという、時計で有名なメーカーが手掛けたジュエリーであること、そして造幣局の検定印が、その出自と品質を雄弁に物語っている。
「美しい…」
翔太は無意識に呟いた。このネックレスが店に来てから、彼の不眠はさらに悪化していた。そして、見る夢の内容が、奇妙な具体性を持ち始めていたのだ。いつも同じ光景。アスファルトの匂い、排気ガスの煙、人々の喧騒。そして、雑踏の中に立つ一人の若い女性。彼女の首元で、見覚えのあるプラチナの喜平が揺れている。夢の中の翔太は、ただその光景を眺めることしかできない、透明な傍観者だった。
その夜も、翔太は寝付けずにいた。深夜2時。諦めてリビングで専門書を開く。手に取ったのは、睡眠科学の権威、柳田正教授の『睡眠と記憶の相互作用:海馬と前頭前野における情報再処理のメカニズム』という学術論文だった。
「…ノンレム睡眠、特に徐波睡眠がエピソード記憶の固定化に寄与する一方、レム睡眠は手続き記憶の強化と、感情的な記憶の処理に重要な役割を果たす。レム睡眠中、脳は扁桃体の活動を抑制し、情動的な出来事を客観的な記憶へと変換するプロセスを行う。これを『夜間療法』と呼ぶ研究者もいる…」
難しい術語の羅列が、かえって意識を覚醒させてしまう。翔太はため息をつき、書斎に向かった。そして、まるで何かに導かれるように、金庫からあの喜平ネックレスを取り出した。月明かりが差し込む部屋で、それは静かに、しかし確かな存在感を放っている。
「お前が来てから、俺の夜はめちゃくちゃだ」
独り言ち、彼はネックレスを自らの首にかけた。ひんやりとしたプラチナの感触が、肌に馴染む。その瞬間、今まで感じたことのないほどの強烈な眠気が、彼の全身を襲った。抗う間もなく、彼の意識は深い、深い眠りの淵へと引きずり込まれていった。まるで、ネックレスそのものが、彼を眠りの世界へと誘う鍵であるかのように。
第一章:昭和五十五年の目覚め
意識が浮上する。しかし、それはいつもの気怠い朝の覚醒とは全く異なっていた。まず耳に届いたのは、車のクラクションと、甲高い焼き芋屋の呼び声。そして、鼻腔をくすぐる、甘辛い醤油の匂いと、微かな排気ガスの香り。翔太が重い瞼をこじ開けると、視界に飛び込んできたのは、見慣れた自室の天井ではなく、煤けた木目の天井板だった。
「…どこだ、ここは」
慌てて身を起こすと、そこは四畳半ほどの和室。窓の外からは、けたたましいほどの生活音が流れ込んでくる。服装は、昨夜眠りについたはずのパジャマではなく、なぜか窮屈な化学繊維のシャツと、野暮ったいデザインのスラックスに変わっていた。そして、首にはあの喜平ネックレスが、確かな重みをもってかかっている。
混乱したまま部屋を飛び出すと、そこは喫茶店の厨房らしき場所だった。ステンレスのカウンター、サイフォンが並ぶ棚、壁には手書きのメニュー。「ブレンドコーヒー 250円」「ナポリタン 450円」。ありえない価格設定に、翔太の眩暈はひどくなる。
「あら、起きたのね。おはよう、相田さん」
背後から声をかけられ、振り返る。そこに立っていたのは、夢で何度も見た女性だった。歳は二十代半ばだろうか。白いブラウスにエプロンをつけた彼女は、きりりとした眉と、大きな瞳が印象的な、快活な雰囲気の女性だった。
「…あなたは?」
「もう、寝ぼけてるの?私よ、高橋美咲。昨日、うちの店の前で倒れてたあなたを介抱したのよ。記憶、ないの?」
美咲と名乗る女性の言葉に、翔太は絶句した。倒れた記憶など、あるはずもない。彼は昨夜、南船場の自宅で眠りについたのだから。店先に置かれていた新聞の日付を見て、翔太はついに現実を認識せざるを得なかった。
「昭和五十五年十月二十五日」
タイムスリップ。非科学的な、荒唐無稽な言葉が、彼の脳裏をよぎった。しかし、目の前の光景、肌で感じる空気、全てが、ここが1980年の世界であることを物語っていた。そして、彼が正気を保てたのは、首にかけられたプラチナの重みだけが、唯一の馴染みある感触だったからだ。
「すみません…何も、思い出せないんです。自分の名前が相田翔太だということ以外…」
咄嗟に記憶喪失を装う。それが、この異常事態を乗り切るための唯一の策に思えた。美咲は心底同情したような顔で、翔太を見つめた。
「そうなの…大変だったのね。警察にも届けたけど、身元が分かるまでは、うちで働いてみない?住み込みで。ちょうど人手が足りなかったのよ」
美咲の申し出は、翔太にとって渡りに船だった。こうして、彼は「喫茶たかはし」の店員として、昭和の時代で生活を始めることになったのだ。仕事は、コーヒーの淹れ方から、ナポリタンの調理、そして美咲の父である頑固なマスター・源治の機嫌の取り方まで、覚えることばかりだった。しかし、令和の価値観に凝り固まった翔太にとって、この時代は驚きと発見の連続でもあった。人々は不便さをものともせず、力強く生きている。アナログなコミュニケーションが、そこかしこで温かい人間関係を育んでいた。
そして何より、翔太の心を捉えたのは、美咲の存在だった。彼女は、いつも太陽のように明るく、店の看板娘として常連客から愛されていた。仕事の合間に見せる真剣な表情、客の子供に向ける優しい笑顔、その一つひとつが、翔太の心に深く刻まれていく。いつしか、翔太は美咲に惹かれている自分に気づいていた。それは、現代で感じたことのない、純粋で、抗いがたい感情だった。
しかし、二人の間には、見えない壁が存在した。美咲には、佐藤健一という婚約者がいたのだ。健一は、地元の不動産会社の社長の息子で、高価なスーツに身を包み、高級車を乗り回していた。彼は店の常連ではあったが、翔太に対しては、初対面の時からあからさまな敵意を向けてきた。
「美咲、こいつはどこの馬の骨だ。いつまでこんな得体の知れない男を置いておくつもりだ」
「健一さん、やめて。相田さんは記憶がなくて困っているの。私が助けてあげたいの」
「お前のお人好しにも困ったもんだな。いいか、美咲は俺の婚約者なんだ。変な気を起こすなよ、記憶喪失さん」
健一が帰った後、店の空気はいつも重くなった。美咲は、翔太に申し訳なさそうに微笑むが、その笑顔にはどこか翳りが見えた。翔太は、彼女が健一との関係に、心から満足しているわけではないことを見抜いていた。だが、自分はこの時代の人間ではない。いつかはいなくなる身。彼女の人生に、これ以上踏み込むべきではない。翔太は、自らの想いに蓋をしようと、必死に自分に言い聞かせるのだった。
第二章:ネックレスの記憶と睡眠の深化
昭和の生活にも慣れてきたある夜、翔太は再び柳田教授の論文の断片を思い出していた。いや、思い出すというより、彼の知識がこの状況を分析しようと、自然に働き始めたのだ。
「…記憶は単一のプロセスではない。符号化、貯蔵、想起の三段階からなる。タイムスリップという現象が、もし仮に何らかの記憶の想起プロセスに関わっているとしたら…このネックレスは、その貯蔵媒体、あるいはトリガーとして機能しているのではないか?」
彼は、首のネックレスに触れた。このプラチナの塊は、単なる物質ではない。それは、過去の誰かの記憶、あるいは強い情念を「貯蔵」しているのではないか。そして、翔太の脳が、特定の条件下でその情報を「想起」し、五感で体験している。それが、このタイムスリップの正体ではないか、と。
その仮説を裏付けるかのように、翔太が見る夢は、さらに鮮明かつ具体的になっていった。それはもはや、傍観者としての夢ではなかった。彼は、一人の若い男性の視点で、世界を体験していた。手には、設計図らしき紙。目の前には、建設途中のビル。そして、隣には、若き日の美咲の祖母らしき女性が、幸せそうに微笑んでいる。
『このビルが完成したら、一番上のレストランで食事をしよう。君のために、最高の席を予約するよ』
『嬉しいわ、昭一さん。でも、本当にいいの?私なんかと…』
『何を言うんだ。君といる時が、俺は一番幸せなんだ。このネックレスは、その約束の証だ』
男性―昭一―の手が、女性の首に、あの喜平ネックレスをかける。夢の中の翔太は、昭一の喜びと、女性への深い愛情を、まるで自分の感情であるかのように感じていた。そして、同時に、二人の間に横たわる、家柄の違いという障壁に対する、昭一の苦悩までもが、痛いほど伝わってきた。
目覚めた翔太の頬を、涙が伝っていた。これは、誰の涙だ?昭一のか、それとも、彼の感情に同調した自分のか。
この夢をきっかけに、翔太は自分の睡眠を、より意識的にコントロールしようと試み始めた。彼は、眠りにつく前に、ネックレスに強く意識を集中させ、昭一と、美咲の祖母であるさちの物語を知りたい、と念じるようになった。
さらに、彼は睡眠の質を高めるために、現代の知識を総動員した。
まず、食事。夕食は就寝の3時間前までに済ませ、トリプトファンを多く含む牛乳を温めて飲むようにした。次に、入浴。38度から40度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かり、深部体温を一度上げ、それが下がるタイミングで眠りにつくように調整した。そして、最も効果があったのは、瞑想だった。呼吸に意識を集中させ、雑念を払い、脳をリラックスさせる。
これらの試みは、驚くべき効果をもたらした。翔太は、夢の内容を、ある程度コントロールできるようになったのだ。彼は、昭一とさちの、幸せなデートの記憶、将来を語り合う希望に満ちた会話、そして、さちの両親から、昭一との交際を猛反対される辛い場面を、追体験していった。
さちの家は、この地域の旧家であり、彼女には親が決めた許嫁がいた。一方、昭一は、才能ある建築家ではあったが、地方から出てきたばかりの、身寄りのない青年だった。二人の恋は、最初から障害に満ちていたのだ。
そして、翔太はついに、二人の別れの場面を夢で見た。
雨が降る公園のベンチで、さちは泣きながら昭一に告げた。
『ごめんなさい、昭一さん。私、もうあなたには会えない。家には逆らえないわ』
『そんな…約束したじゃないか。諦めないでくれ、さちさん!』
『無理よ…。このネックレス、お返しします』
『いや、それは君が持っていてくれ。いつか、必ず君を迎えに行くと、俺が誓った証だ。俺は、諦めない』
しかし、昭一がさちを迎えに行く日は、永遠に来なかった。彼は、無理な仕事がたたり、ビルの建設現場で事故に遭い、若くしてこの世を去ってしまったのだ。
全ての記憶を追体験し終えた朝、翔太は虚脱感に襲われていた。このネックレスは、昭一の、届かなかった想いの結晶なのだ。そして、それは時を超え、今、自分を通じて、何かを訴えかけようとしている。
その日の午後、店に美咲の母、千代がやってきた。彼女は、翔太が首にかけたネックレスを見て、懐かしそうに目を細めた。
「そのネックレス…母の形見によく似ているわ。母はね、亡くなるまで、若い頃にもらった大切なものだって、ずっと大事にしていたのよ」
千代の言葉で、全てが繋がった。このネックレスは、間違いなく、さちが昭一から贈られたものだ。そして、何かの巡り合わせで、一度は手放されたものが、時を超えて、翔太の元へやってきたのだ。
翔太は、決意した。この物語を、ここで終わらせてはいけない。昭一の無念の想いを、そして、さちが最後まで抱き続けたであろう彼への愛情を、然るべき形で成就させなければならない。それが、この時代に自分が来た理由なのだ、と。
第三章:情動の波紋と決断の時
昭一とさちの悲恋を知ってから、翔太の美咲に対する態度は、微妙に変化した。彼女の中に、祖母であるさちの面影を見てしまうのだ。健一との関係に悩み、自分の気持ちに正直になれないでいる美咲の姿が、家柄の違いに苦しみ、愛する人との別れを選ばざるを得なかったさちの姿と重なった。
「過去は、繰り返すべきじゃない」
翔太は、強くそう思うようになった。彼のその思いは、無意識のうちに言動に表れ、美咲との距離をさらに縮めることになった。
ある日、美咲が健一とのデートの帰りに、泣きながら店に戻ってきた。健一が、結婚式の段取りを一方的に決め、彼女の意見を全く聞こうとしなかったのだという。
「私、まるで物みたいに扱われるの…健一さんの家のための、トロフィー人形みたい。もう、嫌…」
しゃがみ込んで嗚咽する美咲の肩を、翔太はそっと抱いた。
「美咲さん。君は、君の人生を生きるべきだ。誰かのための人形になる必要なんてない」
「でも…私には、何もないわ。この店だって、いつまで続けられるか…」
「君には、君自身がいるじゃないか。優しくて、強くて、周りの人を笑顔にする力がある。それは、誰にも真似できない、素晴らしい価値だよ」
翔太の言葉は、温かく、美咲の凍てついた心を溶かしていった。彼女は、翔太の胸に顔をうずめ、子供のように泣きじゃくった。その時、二人の間には、もはや友情以上の、確かな感情が通い合っていた。
この出来事は、健一の嫉妬の炎に油を注ぐ結果となった。彼は、翔太を店の外に呼び出し、殴りかかってきた。
「貴様、美咲をどうするつもりだ!あいつを誑かしやがって!」
「僕は、美咲さんの意志を尊重したいだけだ。彼女を物のように扱うあなたに、その資格があるとは思えない」
「黙れ!記憶喪失のフリをしやがって、本当は何者なんだ!」
もみ合いになる二人を、美咲が必死に止めた。その騒ぎを聞きつけ、近所の人々も集まってくる。この一件で、三人の関係は、もはや修復不可能な段階にまでこじれてしまった。
翔太は、この時代に、これ以上留まるべきではない、と感じ始めていた。自分の存在が、美咲を追い詰めている。そして、昭一の想いを成就させるという目的を果たすためには、一度、令和の時代に戻り、客観的な情報を集める必要があるかもしれない。
彼は、再び睡眠に意識を集中させた。「帰りたい。令和の時代に、一度だけ帰りたい」。そう強く念じながら、眠りについた。しかし、彼の意識は、過去の記憶に引き戻されるばかりで、未来への扉は開かれなかった。
なぜだ?翔太は焦った。そこで、彼は再び柳田教授の論文の一節を思い出す。
「…レム睡眠中の夢は、単なる記憶の再生ではない。それは、未来のシミュレーションとしての機能も持つ。脳は、過去の経験に基づき、起こりうる未来のシナリオを複数生成し、その際のリハーサルを行っているのだ。このプロセスは、生存戦略上、極めて重要である…」
未来のシミュレーション。ならば、自分が令和の時代に帰るためには、この昭和の時代で、何かを「完了」させる必要があるのではないか。昭一とさちの物語に、何らかの結末を与える。そして、美咲との関係にも、一つのけじめをつける。それが、未来への扉を開く鍵なのではないか。
翔太は、腹を括った。彼はまず、美咲に全てを話すことを決意した。タイムスリップしてきたこと、ネックレスに宿る記憶のこと、そして、彼女の祖母の悲しい恋物語のこと。常識的に考えれば、到底信じてもらえないだろう。狂人だと思われるかもしれない。だが、彼女になら、信じてもらえるかもしれない。そんな不思議な確信が、彼にはあった。
その夜、閉店後の「喫茶たかはし」で、翔太は美咲と二人きりで向き合った。
「美咲さん、今から、信じられないような話をする。でも、どうか、最後まで聞いてほしい」
翔太は、ゆっくりと、自分の身に起きた全ての出来事を語り始めた。南船場のジュエリーショップ、不眠症、ネックレスとの出会い、そして、この昭和五十五年へのタイムスリップ。美咲は、最初は驚きに目を見開いていたが、やがて、真剣な表情で、黙って彼の話に耳を傾けていた。
そして、翔太が、彼女の祖母さちと、昭一という建築家の悲恋について語り始めた時、美咲の瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。
「…そんなことが…。おばあちゃん、何も言ってなかったわ。ただ、若い頃に、本当に愛した人がいたって、一度だけ、寂しそうに笑っていたのを思い出した…」
「このネックレスは、その昭一さんの、さちさんへの想いの証なんだ。そして、僕は、この想いを、時を超えて届けるために、ここに来たんだと思う」
全てを語り終えた翔太に、美咲は尋ねた。
「翔太さん…あなたは、いつか、あなたの時代に帰ってしまうのね?」
「…ああ。そのために、やらなければならないことがある」
沈黙が、二人を包んだ。美咲は、涙を拭うと、決意を秘めた目で、翔太を見つめ返した。
「わかったわ。私も、手伝う。おばあちゃんの想いを、そして、昭一さんの想いを、私たちが叶えてあげるのよ。そして、私も、決めなくちゃいけない。自分の人生を」
美咲の言葉は、翔太に大きな勇気を与えた。二人の心は、時を超えた悲恋を成就させるという、一つの目的のために、固く結ばれたのだった。
第四章:白金の誓いと時の扉
美咲という強力な協力者を得た翔太の行動は、加速した。二人はまず、昭一に関する情報を集めることから始めた。美咲が、母の千代に、それとなく祖母の過去について尋ねると、千代は古いアルバムを押し入れの奥から出してきた。そこには、若き日のさちと、見知らぬ青年が、少し照れたように寄り添って写っている写真があった。写真の裏には、「昭和28年、春。昭一さんと」という、さちの小さな文字が記されていた。
「この人が、昭一さん…」
翔太は、夢で見たままの、誠実そうな青年の姿に、胸が熱くなるのを感じた。さらに、二人は古い電話帳や図書館の資料を調べ、昭一が「宮田昭一」という名前の建築家で、当時、大阪でいくつかのビルの設計を手掛けていたことを突き止めた。そして、彼が事故で亡くなったのが、昭和29年の冬であったことも。
「おばあちゃんと別れて、一年も経たないうちに…」
美咲は、言葉を詰まらせた。
彼らの目的は、明確になった。昭一がさちに託した「いつか迎えに行く」という叶わなかった想いを、何らかの形で現代に伝えることだ。しかし、どうやって?昭一は既にこの世におらず、さちも数年前に亡くなっている。
ここで、翔太はある仮説に思い至る。
「…柳田教授の論文に、こんな一節があった。『記憶の外部化と継承に関する一考察』。人間の記憶は、脳内だけでなく、日記や写真、あるいは特定の品物といった外部媒体にも保存され、世代を超えて継承されうると。このネックレスは、まさにその記憶の外部化装置なんだ」
ならば、このネックレスに、新たな記憶を「上書き」することはできないだろうか。昭一の無念と、さちの悲しみを、昇華させるような、新しい物語を。
翔太は、美咲に一つの提案をした。
「宮田昭一さんが設計したビルを探し出して、そこに行こう。そして、このネックレスに、僕たちの想いを託すんだ。『あなたたちの想いは、確かに受け継がれました』と」
幸いにも、昭一が設計したビルの一つは、今も大阪市内に現存していることが分かった。二人は、休日を利用して、そのビルを訪れた。それは、昭和の面影を色濃く残す、レトロでありながらも、洗練されたデザインの美しいビルだった。
屋上は、一般には開放されていなかったが、翔太と美咲は、ビルの管理人に事情を話し、特別に入れてもらうことができた。夕暮れの光が、大阪の街を黄金色に染めている。
「昭一さんは、この景色を、さちさんと一緒に見たかったんだろうな…」
翔太の呟きに、美咲は黙って頷いた。
翔太は、首からネックレスを外し、二人でそれを握りしめた。
「宮田昭一さん、さちさん。あなたたちの物語は、ここで終わりじゃありません。あなたたちの深い愛情は、時を超えて、僕たちに確かに届きました。どうか、安らかに…」
美咲も、祈りを込めて続けた。
「おばあちゃん、昭一さん。あなたたちの分まで、私は、自分の気持ちに正直に生きます。幸せになります」
二人が祈りを終えた、その瞬間。翔太の脳裏に、今まで見たことのない、温かい光景が流れ込んできた。それは、穏やかな表情で微笑み合う、昭一とさちの姿だった。二人は、翔太と美咲に優しく頷きかけると、光の中に溶けるように消えていった。
翔太は、ネックレスに宿っていた重く悲しい情念が、ふっと軽くなったのを感じた。それは、昭一とさちの魂が、ようやく解放された証のように思えた。
ビルからの帰り道、美咲は、きっぱりとした口調で言った。
「私、健一さんとの婚約を、正式にお断りする。そして、お父さんを説得して、この店を継ぐわ。私の力で、この店を守っていく」
彼女の顔には、もう迷いの色は見えなかった。自分の足で、自分の人生を歩んでいこうとする、強い意志が輝いていた。翔太は、そんな彼女を、心から誇らしく思った。
そして、その夜。翔太は、眠りにつく前に、ネックレスを手に取り、強く念じた。
「ありがとう、昭一さん、さちさん。そして、さようなら、美咲さん」
彼の心は、感謝と、そして、美咲との別れに対する切なさで満たされていた。これで、この時代での自分の役目は終わった。彼が眠りに落ちると、意識は、今度こそ、未来へ、令和の時代へと向かって、急速に浮上していくのを感じた。それは、悲しい別れであると同時に、一つの物語を完結させたという、確かな達成感を伴う、不思議な感覚だった。
終章:令和のブランドクラブ
目覚まし時計の電子音が、翔太を現実へと引き戻した。見慣れた自室の天井。カレンダーは、昭和五十五年から進んで、彼が去ったはずの令和の時代を指している。
「…帰ってきたのか」
翔太は、ゆっくりと身を起こした。数ヶ月に及んだ昭和での日々が、まるで昨夜見た、長編の夢だったかのように感じられる。しかし、それは決して夢ではなかった。彼の手元には、あの喜平ネックレスが、確かな存在感を放っている。そして、ネックレスの輝きは、以前よりも、どこか優しく、穏やかになったように見えた。
彼の不眠症は、嘘のように消え去っていた。夜は深く、穏やかな眠りが訪れ、朝はすっきりと目覚めることができる。それは、心に抱えていた、時を超えた宿題を、ようやく終えることができたからだろう。
翔太は、まず、宮田昭一の親族を探すことから始めた。幸い、現代のインターネットを使えば、情報を集めるのはそれほど難しくない。彼は、昭一の甥にあたるという、高齢の男性に辿り着くことができた。
翔太は、彼を訪ね、叔父である昭一と、高橋さちという女性の悲恋について語った。甥の男性は、驚きながらも、翔太の話を真剣に聞いてくれた。そして、彼が語った。
「そういえば、叔父の遺品の中に、一通の、宛先のない手紙が残っていました。さち、という女性に宛てた、ラブレターでしたよ」
その手紙は、昭一が事故に遭う直前に書いたもので、そこには、さちへの変わらぬ愛と、彼女を必ず迎えに行くという、強い決意が綴られていた。
一方、翔太は、高橋美咲のその後も、気になっていた。彼女は、無事に店を継ぐことができたのだろうか。健一との関係は、どうなったのだろうか。しかし、それを調べる術は、彼にはなかった。
数週間が過ぎたある日の午後。「ブランドクラブ」のドアベルが鳴り、一人の女性が店に入ってきた。歳は、翔太と同じくらいだろうか。芯の強さを感じさせる、大きな瞳が印象的な女性だった。彼女は、店の中をゆっくりと見渡すと、やがて、翔太のいるカウンターへと歩み寄ってきた。
そして、ショーケースの中に飾られている、あの喜平ネックレスに、彼女の視線が留まった。
「素敵なネックレスですね…どこか、懐かしい感じがします」
その声、その話し方。翔太の心臓が、大きく高鳴った。まさか。そんなはずはない。
「お客様…失礼ですが、お名前を伺ってもよろしいですか?」
女性は、少し不思議そうな顔をしたが、にこやかに名乗った。
「高橋、美咲と申します」
その瞬間、時が止まった。翔太の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。彼女は、覚えていないかもしれない。転生した魂が、過去の記憶を全て留めているわけではないだろう。だが、翔太には分かった。目の前にいるのは、紛れもなく、彼が愛した、あの高橋美咲なのだ。
そして、美咲もまた、翔太の顔をじっと見つめるうちに、その瞳に、困惑と、そして、何かを思い出すかのような、切ない色が浮かんだ。
「私たち…どこかで、会ったこと、ありませんか?夢の中で、だったかしら…」
翔太は、涙を拭い、精一杯の笑顔を作った。彼は、ショーケースから、あの喜平ネックレスを取り出すと、そっと美咲の前に差し出した。
「これは、時を超えて、あなたに会うために、ずっと待っていたネックレスです。そして、僕も」
白金の鎖が、二人の運命を、再び結びつけようとしていた。南船場の片隅で始まった、時を超えたジュエリーストーリーは、令和の時代に、新しい、輝かしいハッピーエンドを迎えようとしていた。二人の物語は、まだ始まったばかりだ。
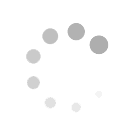




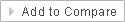
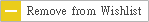
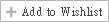







 Malaysia
Malaysia





