0.94カラットの厄除け(やくよけ)
序章:南船場に眠る「傷」
大阪、南船場。御堂筋の喧騒から一本裏手に入ると、そこはまるで時間が緩やかに流れる別の世界だった。ガス灯を模した街灯が、夕暮れの石畳をノスタルジックな光で濡らしている。この街で三代続くジュエリーセレクトショップ「ブランドクラブ南船場」は、その歴史の重みと格式を、磨き上げられたマホガニー※Mahogany trees are items that are in conflict with the Washington Treaty and cannot be shipped internationally. の扉の奥に静かに湛えていた。しかし、三代目オーナーである倉田美咲(くらた みさき・30歳)の心の中は、店の穏やかな雰囲気とは裏腹に、凪いだ海の底に溜まる澱のように、重く、冷たく沈んでいた。
閉店後の静寂が、思考の輪郭を嫌というほど鮮明にする。美咲は、ベルベットのトレーの上で、まるで孤高を保つかのように鎮座する一つの指輪に視線を落とした。
ティファニーの、クラシックな6本爪セッティングのソリティアリング。
その美しさは絶対的だった。鑑定士として叩き込まれた知識と経験が、それが寸分の狂いもない最高品質のダイヤモンドであることを正確に告げている。ティファニーがその威信をかけて発行した鑑定書が、その事実を雄弁に物語っていた。
光を全方位から取り込み、内部で完璧な反射を繰り返して生まれるブリリアンス、虹色の光の分散であるファイア、そして表面でまたたくシンチレーション。そのどれもが、教科書に載せたいほどに完璧な「トリプルエクセレント」。
だが、その完璧なスペックの中に、たった一つ、商業的な「傷」が存在した。0.94カラット、という石目。
「0.94(苦しむ)」。
その古風で非科学的な語呂合わせは、しかし、人の心を縛る呪いのようにこの国のブライダル市場に棲みついている。特に、美咲の店の主たる顧客である、古くからの富裕層や格式を重んじる人々にとっては、それは致命的な欠陥に等しかった。1カラットという心理的な大台に、ほんの僅か0.06カラット届かない不完全さ。それは、まるで幸せの頂点に指をかけながら、ついに登りきることのできないもどかしさを、残酷なまでに象徴しているかのようだった。
三ヶ月前、美咲はこのリングを、業界でも注目される遺品オークションで競り落とした。出品リストの中にこれを見つけた瞬間、彼女の鑑定士としての血が騒いだのだ。原石のポテンシャルを最大限に引き出すため、カラット数をわずかに犠牲にしてでも完璧なカットを追求した、職人の誇り高い仕事の痕跡。これからの時代、若い世代は古いジンクスに囚われず、こうした本質的な美しさを見抜いてくれるはずだ。これは、偉大な父から受け継いだこの店に、新しい風を吹き込むための、私自身の挑戦だ。そう信じて疑わなかった。
しかし、現実は冷酷だった。ショーケースに並べて以来、このリングに心惹かれる顧客はいても、最後の最後で石目を聞くと、皆一様に顔を曇らせ、まるで触れてはいけないものに触れてしまったかのように、そっとトレーに戻すのだった。
『だから言うたんや、美咲。宝石は夢を売る商売や。スペックや理屈やない。人が見て、心から「縁起がええ」と思えるもんやないとあかん。0.94なんて中途半端なもん、誰も祝い事には使わんよ』
電話口で聞こえた父・健介(けんすけ)の、呆れと憐れみが入り混じった声が、耳の奥で何度も再生される。一年前に健介から店を譲り受け、美咲は必死だった。祖父から父へ、父から自分へと受け継がれた店の暖簾。その重圧は、想像を絶していた。伝統を守りながらも、時代遅れになりつつある店の空気を変えたい。その焦りが、今回の仕入れに繋がったのかもしれない。結果として、このリングは「美咲の独りよがりな挑戦の失敗作」として、店の在庫に、そして彼女の心に、重くのしかかっている。
管理番号「F4434」と記されたタグが、まるで敗者の烙印のように見えた。
美咲自身の人生もまた、このリングに重なって見えた。半年前、彼女は三年間付き合った恋人、聡(さとし)との婚約を破棄されたばかりだった。相手は取引先の銀行の頭取の息子で、誰もが羨むような「完璧な」相手だった。しかし、彼は美咲が家業を継ぐことに最後まで反対した。「女がいつまでも職人の真似事みたいなことをしていないで、家庭に入って僕を支えるのが一番の幸せだろう。倉田さんのところは、お父さんがまだお元気なんだから、君が無理して継ぐ必要はない」。その言葉に、美咲の中の何かがぷつりと切れた。彼女の人生、彼女が愛する仕事を、彼はスペックでしか見ていなかった。彼にとっての「完璧な妻」という枠に、私は収まらなかったのだ。
幸せの象徴である婚約指輪を売る仕事に、深く打ちのめされた自分がいる。幸せの絶頂にいるはずのカップルを、心から祝福できない自分がいる。まるで、1カラットに届かないこのダイヤモンドのように、自分もまた、世間が求める「幸せの基準値」に満たない不完全な存在なのではないか。
そんな自己嫌悪が、ショーケースのガラスThe page has a fragile description, and fragile items cannot be shipped by sea. They can only be shipped by air. If the goods are not fragile, they can be shipped by air. に映る自分の顔を歪ませていた。
第一章:「逆縁起」という選択
その男性が店に現れたのは、初夏の光が眩しくなり始めた土曜日の午後だった。歳の頃は三十代半ば。高価なスーツを着ているわけではない。藍染の作務衣に似た風合いの、上質なリネンのジャケットを、まるで長年着込んだかのように自然に着こなしている。その佇まいには、都会の喧騒とは無縁の、静かで深い落ち着きがあった。
「こんにちは。少し、拝見してもよろしいですか」
穏やかで、芯のある声だった。彼は、多くの客のようにショーケースを端から順に眺めるのではなく、まるでそこに漂う「気」を感じ取るかのように、ゆっくりと店内を歩いた。そして、何の迷いもなく、あの0.94カラットのリングの前で足を止めた。彼の視線は、他のどの宝石にも向けられることなく、ただ一点に吸い寄せられていた。
「…これを、見せていただけますか」
美咲は、またか、と内心で小さくため息をついた。このリングには、人を惹きつける魔力のようなものはあるのだ。しかし、どうせ石目を知れば、がっかりされるに決まっている。彼女は、半ば諦めの気持ちを押し殺し、プロフェッショナルな笑顔を作ると、リングをトレーに乗せてカウンターへ運んだ。
男性は、差し出されたルーペを手に取ると、驚くほど手慣れた様子でダイヤモンドを覗き込んだ。その指先は、細く、長く、そして何かを慈しむように、ものに触れる。まるで、石と対話しているかのようだ。
「素晴らしい仕事ですね。寸分の狂いもない。この小さな結晶の中に、宇宙の法則が凝縮されているかのようだ。これほどの輝きを引き出すために、どれほどの集中力と計算が込められているか…」
それは、鑑定士である美咲ですら、普段は意識しない、作り手の魂への敬意に満ちた言葉だった。美咲は、この客がただ者ではないことを直感した。彼の言葉には、表面的な美しさを超えた、物の本質を見抜く力があった。
「ありがとうございます。カット、ポリッシュ、シンメトリー、全てが最高評価のものです」
「ええ、分かります。このファセットの一つ一つが、完璧な角度で光を受け渡し合っている。…そして」
男性はルーペを置くと、鑑定書に目を落とした。美咲は、思わず身構えた。次に来るであろう、落胆の言葉を予測して。心臓が、嫌な音を立てて脈打つ。
「0.94カラット、ですか。なるほど」
彼の口調に、落胆の色は微塵もなかった。むしろ、何かを探し当てたかのような、静かな満足感が漂っていた。彼は顔を上げ、まっすぐに美咲の目を見ると、悪戯っぽく微笑みながら言った。
「面白い。…いや、素晴らしい。まさに、これです。私が探していたのは」
「…え?」
美咲は、自分の耳を疑った。聞き間違いだろうか。
「お客様、失礼ですが…0.94という数字の、いわゆる語呂合わせはご存知で…」
「ええ、もちろん存じています。『苦しむ』でしょう?」
彼は、こともなげに言った。まるで、天気の話でもするかのように。
「だからこそ、です。だからこそ、これを選びたい」
意味が分からず、呆然とする美咲に、彼は改めて向き直り、自己紹介をした。
「申し遅れました。私、橘 恭平(たちばな きょうへい)と申します。京都の片隅で、金継ぎの仕事をしております」
金継ぎ(きんつぎ)。割れたり欠けたりした陶磁器を、漆で接着し、金や銀で装飾して修復する、日本の伝統的な技法。美咲の頭の中で、バラバラだったピースが一つの像を結び始めた。傷を、美に変える仕事。
「金継ぎの世界では」と恭平は続けた。「傷は、決して欠点ではありません。むしろ、その器が辿ってきた歴史そのものであり、新しい景色となるべき、かけがえのない個性です。割れてしまったからこそ、金で装飾することで、元の姿よりもさらに価値のある、唯一無二の存在へと生まれ変わる。私たちは、その哲学を大切にしています」
彼の言葉は、静かだが、圧倒的な説得力を持って美咲の心に響いた。まるで、固く閉ざされていた心の扉が、ゆっくりと開かれていくような感覚だった。
「日本では昔から、『逆縁起(さかえんぎ)』という考え方があるのをご存知ですか」
「逆縁起…?」
「ええ。例えば、厄年にあえて大きな買い物をしたり、家を新築したりする。そうすることで、『これ以上の厄が訪れませんように』という強い願いを込める。また、鬼瓦のように、あえて恐ろしい形相のものを魔除けとして置く文化もあります。一見、不吉とされるもの、悪いとされているものをあえて自分の元に引き受けることで、それを乗り越える力とし、より大きな幸運を呼び込むための、いわば積極的な『お守り』にするのです」
恭平は、再びダイヤモンドに目を落とした。その輝きは、彼の瞳の中で、まるで呼応するかのように一層強くまたたいた。
「この指輪を、婚約指輪として求めたいのです。これからの人生、山もあれば谷もあるでしょう。楽しいことばかりではない。苦しいこと、悲しいことも、きっと二人で経験していくことになる。だからこそ、私たちは、この『0.94(苦しむ)』を、あえて選びたい。この指輪を、私たちの『厄除け』のお守りとするのです。これから訪れるであろう、あらゆる苦しみを、このダイヤモンドが一身に引き受け、二人の絆の輝きに変えてくれる。そう信じて、身に着けたいのです」
それは、美咲がこれまでの人生で聞いた、どんなセールストークよりも、どんな愛の言葉よりも、力強く、美しい、愛の哲学だった。
「傷」だと思っていた0.94という数字が、今、この瞬間、最も尊い「お守り」へと生まれ変わった。美咲は、言葉を失い、ただ目の前の男性の、深く澄んだ瞳を見つめ返すことしかできなかった。目頭が、不意に熱くなった。
第二章:二人が紡ぐ物語
数日後、恭平は、婚約者だという女性を連れて再び店を訪れた。森山 柚月(もりやま ゆづき)と名乗った彼女は、大学で日本美術史を研究し、現在は美術館で学芸員として働いているという。知的で、柔らかな物腰の中に、凛とした芯の強さを感じさせる女性だった。
美咲は、恭平が語った「逆縁起」の哲学を、柚月がすんなりと受け入れられるだろうかと、少し心配していた。いくら素晴らしい哲学でも、一生に一度の婚約指輪に「苦しむ」という数字を選ぶのは、女性にとって勇気がいることだろう。
しかし、それは全くの杞憂だった。
柚月は、恭平から説明を受ける前から、リングを一目見るなり、愛おしそうに微笑んだ。
「まあ、きれい…。完璧に美しいのに、どこか儚げで…。でも、その奥にとても強い意志を感じる輝きですね」
そして、恭平が0.94カラットに込めた想いを、隣で優しく語り始めると、彼女は深く、何度も頷いた。その眼差しは、恭平への絶対的な信頼と、彼の哲学への深い共感に満ちていた。
「素晴らしい考え方だわ、恭平さん。私も、全く同じ気持ちです」
柚月は、美咲に向き直り、自分の専門分野の話をしてくれた。
「日本の美意識には、『わびさび』という言葉に代表されるように、不完全さの中にこそ美を見出すという思想が、古くから根付いています。例えば、千利休が愛した茶器には、意図的に歪められたり、左右非対称であったりするものが少なくありません。完璧に整えられたものよりも、少し欠けていたり、歪んでいたりするものにこそ、人の心の温かみや、時間の経過といった、いわゆる『物語』が宿る。私たちは、そういうものに心惹かれる文化を持っているんです」
彼女は、そっとリングを指にはめてみた。その白くしなやかな指に、0.94カラットのダイヤモンドは、まるで最初からそこにあるべきだったかのように、完璧に収まった。
「私たちの人生も、きっと完璧ではないでしょう。喧嘩もするし、すれ違うこともあるかもしれない。でも、その度に、この指輪を見るんです。この『0.94』という数字を見るたびに、私たちは思い出す。『ああ、私たちは、苦しみを乗り越えるって、一緒に誓ったんだ』って。傷つくことを恐れるのではなく、傷ついたら、恭平さんの金継ぎのように、もっと美しい絆で修復していけばいい。この指輪は、そのための勇気を、きっと私たちに与えてくれます」
二人の間で交わされる視線は、深く、穏やかで、絶対的な信頼に満ちていた。彼らは、宝石のスペックや、世間的な評価で愛を測るのではない。自分たちだけの、唯一無二の物語を、この指輪を核として、今まさに紡ぎ始めようとしていた。
美咲は、二人の姿に、いつしか自分の姿を重ねていた。婚約破棄という、自分につけられた「傷」。不完全な自分。その傷を隠し、欠点だと嘆くことしかできなかった自分。しかし、彼らは教えてくれた。傷は、歴史であり、個性であり、乗り越えることで、より深い美しさに変わるのだと。聡との関係も、完璧を求めるあまり、お互いの「不完全さ」を許容できなかった結果だったのかもしれない。
その日の会計を終え、恭平と柚月は、深々と頭を下げて店を出ていった。美咲は、二人の後ろ姿が見えなくなるまで、店の入り口で見送った。胸の中に、温かいものが、じんわりと広がっていくのを感じた。それは、商品を売った満足感とは全く違う、魂が救われたような、静かで満ち足りた感覚だった。
第三章:世代を超えた対峙
あの指輪が売れてから、店の空気は明らかに変わった。いや、変わったのは、美咲自身の心だった。ショーケースの宝石たちが、以前よりも生き生きと輝いて見える。訪れる客との会話も、心から楽しめるようになった。彼女の中で、仕事への誇りと情熱が、静かに、しかし確実に再燃していた。
そんなある日、店のドアベルが、いつもより少しだけ重々しい音を立てた。父の健介だった。引退してからは、よほどのことがない限り店には顔を出さない父が、険しい表情で立っている。その手には、業界の月刊誌が握られていた。
「美咲、ちょっと話がある」
父は、事務所の椅子にどっかと腰を下ろすと、単刀直入に切り出した。
「先日、昔からの馴染みのお客さん、宝石タナカの社長と話してて、妙な噂を耳にしたんや。うちの店が、あの『0.94』の指輪を、こともあろうに婚約指輪として売った、とな。まさかとは思うが、本当か?」
その声には、怒りというよりも、深い失望の色が滲んでいた。美咲は、息を呑んだ。好事魔多し。業界は、狭い世界だ。誰かが、面白おかしく噂を広めたのだろう。
「…本当よ、お父さん」
「なんやと!?」
健介は、テーブルを叩かんばかりの勢いで立ち上がった。
「お前、何を考えとるんや! あの指輪は、お前の独りよがりの失敗やなかったんか。それを、世間知らずの若いお客さんを言いくるめて売りつけたとでもいうんか! 先代、つまりお前のじいちゃんからわしが受け継いで、大事に守ってきたこの店の信用に泥を塗る気か!」
父の怒声が、事務所に響き渡る。以前の美咲なら、きっとここで萎縮し、言い訳をし、泣き出していただろう。彼の言葉は、彼女が心の奥底で恐れていた、自分自身への疑念そのものだったからだ。
しかし、今の彼女は違った。彼女は、静かに立ち上がると、父の目をまっすぐに見つめ返した。その瞳に、怯えの色はなかった。
「違うわ、お父さん。私は、何も言いくるめてなんかいない。むしろ、私の方が、お客様に教えられたの。物の価値とは何か、ということを。そして、お父さんや、おじいちゃんが大切にしてきた、『縁起』というものの、もう一つの側面を」
美咲は、恭平と柚月のことを、彼らが語ってくれた「逆縁起」と「金継ぎ」の哲学を、一言一言、丁寧に父に伝えた。悪いとされるものをあえて引き受け、それを乗り越える力に変えるという、日本の伝統的な強さと美しさ。傷を隠すのではなく、慈しみ、新たな価値を与えるという思想。
「お父さんが大切にしてきた『縁起』という考え方は、もちろん尊重するわ。災いを避けたいと願う人の心に寄り添うのも、私たちの仕事。でも、縁起には、もう一つの形があることを、私は知ったの。ただ悪いことから逃げるだけじゃない。災いを引き受け、福に転じるという、もっと能動的で、力強い祈りの形があるということを」
彼女の声に、震えはなかった。それは、借り物の言葉ではない、彼女自身の体験から生まれた、確信に満ちた言葉だった。
「私は、あの指輪を『傷物』として安売りすることもできた。でも、そうしなかった。なぜなら、あのお客様は、あの指輪の本当の価値を、誰よりも深く理解してくださったから。あの指輪は、彼らにとって、世界で一番縁起のいい、最高のお守りになったの。お客様の幸せを心から願って、その想いに寄り添うのが私たちの仕事なら、私のしたことの、どこが間違っているの?」
健介は、娘の気迫に押され、言葉を失っていた。彼が知っている、いつも自信なさげで、彼の顔色を窺ってばかりいた娘は、もうそこにはいなかった。そこにいたのは、自分の哲学を持ち、自分の言葉で商いをする、一人の自立した経営者だった。彼の知らない間に、娘は、彼が想像もしていなかった形で、成長を遂げていた。
健介は、大きく、長い息を吐くと、再び椅子に深く腰掛けた。
「…逆縁起、か。わしら年寄りは、ただ悪いことから逃げることしか考えんかったが…今の若い連中は、そんな風に考えるんか。…金継ぎの職人さん、か」
その声には、もう怒りの色はなかった。むしろ、自分たちの時代にはなかった、新しい価値観に対する、戸惑いと、ほんの少しの敬意のようなものが感じられた。
「…好きにせい。お前の店や。ただし、中途半端な覚悟でやるな。お客さんの人生を預かるいうことを、絶対に忘れるなよ」
そう言って席を立った父の背中は、少しだけ小さく見えた。それは、寂しさではなく、次の世代へバトンを渡した者の、安堵の背中に見えた。
終章:金継ぎの心
季節が巡り、木々の葉が錦に染まる秋の終わり。美咲の元に、小さな桐の箱が届いた。差出人は、橘 恭平と森山 柚月。結婚式の招待状か何かだろうか、と彼女は思った。
箱を開けた美咲は、思わず息を呑んだ。中に入っていたのは、招待状ではなかった。それは、指輪を一つだけ収めるために作られた、息をのむほどに美しいリングボックスだった。
本体は、年月を経て深い色合いになった桜の古木。木目が、まるで水墨画のように美しい。そして、その蓋には、一筋、繊細で、しかし確かな存在感を放つ金の線が走っていた。金継ぎだ。
添えられた手紙には、恭平の、流れるような美しい筆文字で、こう書かれていた。
『倉田美咲様
秋冷の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
その節は、私たちの人生にとって、最も大切な宝物との出会いをいただき、誠にありがとうございました。
私たちは、先日、京都の小さな神社で、ささやかな結婚式を挙げました。あの指輪は、誓いの言葉と共に、私たちの指で、今も力強く輝いています。喧嘩をした夜も、不安に駆られた朝も、この指輪に宿る誓いと、倉田さんの温かい笑顔を思い出すことで、私たちは何度も救われました。
このリングボックスは、私たちのささやかな感謝の気持ちです。この箱は、私たちが散策中に見つけた、雷に打たれて割れてしまっていた桜の古木から作りました。恭平さんがその割れ目を丁寧に整え、金で継ぎました。あの指輪が持つ物語を、それを収める箱にも宿したかったのです。
傷は、終わりではなく、新しい美しさの始まりである。倉田さんが、あの指輪の価値を信じ、私たちと出会わせてくれたおかげで、私たちはそのことを、人生の揺るぎない誓いとすることができました。
ブランドクラブ南船場の、そして倉田様の未来が、この金の線のように、強く、美しく輝き続けることを、心よりお祈り申し上げます。
橘 恭平・柚月』
美咲の頬を、温かいものが伝った。それは、半年前の自分なら決して流すことのなかった、喜びと感謝の涙だった。婚約破棄という自分の「傷」も、いつかこんな風に、美しい金の線になる日が来るのかもしれない。そう、初めて心から思えた。
彼女は、店のウェブサイトを開き、新しいブログ記事を書き始めた。特定の誰かを非難するのでも、自店の正当性を主張するのでもない。ただ、彼女が学んだ、美しい日本の哲学について、誠実に綴った。
タイトルは、『傷を愛でるということ ―金継ぎと逆縁起の哲学に学ぶ―』。
その記事は、静かに、しかし確実に、人々の心に届き始めた。数日後、一組の若いカップルが、そのブログを読んだと言って店を訪れた。
「私たち、実は一度、婚約を解消しかけたんです。お互いを傷つけてしまって…。でも、もう一度やり直すことに決めて、今日ここに来ました。だから、完璧な指輪じゃなくていいんです。何か、二人で乗り越えていけるような、そんな物語のある指輪が欲しいんです」
美咲は、最高の笑顔で二人を迎えた。その笑顔には、もう一片の曇りもなかった。
「かしこまりました。ぜひ、お手伝いさせてください」
彼女の心の中では、もうあの0.94カラットのダイヤモンドは、「傷」でも「お荷物」でもなかった。それは、彼女自身の「厄除け」となり、店に、そして彼女の人生に、新しい福を呼び込んでくれた、最高のお守りとして輝き続けていた。南船場の優しい光の中で、美咲の新しい物語が、今、静かに始まろうとしていた。
・・・ここまで書いても気になると言われたら、、、しゃあない外人さんお願いしますw
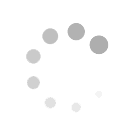




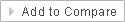
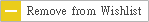
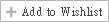












 Malaysia
Malaysia





