過酷な撮影現場と「不気味」な主役たち
映画『ガベージ・パイル・キッズ(The Garbage Pail Kids Movie)』において、予算もスケジュールも味方しなかったことは、今さら驚くようなことではありません。制作陣は公開を急ぐあまり、ありとあらゆる場所で手を抜きましたが、その弊害が最も顕著に、そして無残に表れているのが、タイトルにもなっているキャラクターたちの姿です。彼らが画面に映る時間は、主役にしては短すぎ、かといって、あの不気味で機械的な(アニマトロニクスの)顔を直視するには長すぎる……そんな奇妙な違和感に満ちています。
このキャラクターたちは、俳優がグラスThe page has a fragile description, and fragile items cannot be shipped by sea. They can only be shipped by air. If the goods are not fragile, they can be shipped by air. ファイバーとフォームラテックスで作られた重厚なヘッドを被り、その表情をリモコンで操作することで表現されました。「不潔さ」を売りにしたデザイン自体は悪くありませんでしたが、アニマトロニクスの完成度は、控えめに言ってもお粗末なものでした。顔の筋肉はひきつり、目は意図せず動き、口の動きはセリフと全く噛み合っていません。結果として、制作側の意図を遥かに超えた「不気味の谷」の怪物たちが誕生してしまったのです。
しかし、この責任を、80ポンド(約36kg)もの衣装に身を包んだ7人の小人症の俳優たちに負わせるべきではありません。彼らは、この破天荒な子供向け映画を完成させるために、想像を絶する過酷な環境に耐え抜いたのです。巨大なヘッドのせいで視界はほとんどなく、内部に詰め込まれた電子部品の作動音と防音用のフォームのせいで、周囲の声を聞き取ることすら困難でした。
何より悲惨だったのは、その「暑さ」です。撮影は初夏のカリフォルニアにある倉庫で行われましたが、強い日差しと不十分な空調が重なり、セット内の気温は華氏100度(約38度)を超えました。長回しの撮影では、救急隊員がストップウォッチを手に待機し、俳優たちの休憩時間を厳密に管理しなければならないほどでした。重く息苦しいヘッドの中では数分間呼吸するのも困難で、彼らは文字通り命懸けで演技をしていたのです。
ハリウッドの歴史と小人症俳優のコミュニティ
こうした凄惨な状況は、残念ながらハリウッドの長い歴史の中で、多くの小人症の俳優たちが甘んじて受け入れてきた経験の典型でもあります。彼らのために書かれた役は極めて少なく、その多くは着ぐるみの中での仕事でした。熱く重いゴムやフォームの層に埋もれながら、彼らは演技というよりも、パペット操作やマイムに近い技術を要求されてきたのです。
リトル・ピープル(小人症の人々)がロサンゼルス周辺に多く集まっている背景には、映画産業の歴史が深く関わっています。1939年の映画『オズの魔法使』の撮影のために世界中から100人以上の小人症の人々が呼び寄せられ、その多くが撮影後も西海岸に定住しました。現在でも、アメリカ全土の小人症の人々の約5人に1人が南カリフォルニアを故郷と呼んでいます。
1957年には、名優ビリー・バーティの呼びかけにより、全米規模の非営利団体「リトル・ピープル・オブ・アメリカ(LPA)」が設立されました。LPAは会員の教育、医療、奨学金の支援に加え、社会的な交流の場を提供してきました。当初21人で始まった集まりは、今や全米に7,000人以上の会員を抱える組織へと成長しています。
LPAはまた、映画のキャスティング情報を共有する役割も果たしました。本作に出演した7人の俳優のうち5人も、LPAの会報に掲載されたエキストラ募集を見てキャリアをスタートさせています。
俳優たちの絆と「ハリウッド・ショーティーズ」
本作で「鼻水Beauty and health care products require approval from relevant units before they can be purchased and imported, so we cannot assist in purchasing them. 垂らしのテッシー」を演じたスーザン・ウォリングフォード・ロッシットもその一人です。彼女はLPAのコンベンションで、後に夫となるジョージ・ロッシットと出会い、ロサンゼルスへと移り住みました。彼女の義父アンジェロ・ロッシットは、無声映画時代から100本以上の作品に出演した、業界で最も有名な小人症俳優の一人でした。
スーザン自身もスタント俳優として活躍し、多くの作品で着ぐるみの中に入りました。本作の後には、『バットマン リターンズ』でダニー・デヴィート演じるペンギンの手下である「本物のペンギン」のスーツを着て演じています。ちなみに、このペンギン役のうち3人は本作『ガベージ・パイル・キッズ』の出演者でした。
俳優たちの多くは、ビリー・バーティが1948年に設立したスポーツチーム「ハリウッド・ショーティーズ」の仲間でもありました。このソフトボールやバスケットボールのチームは、自分たちよりも遥かに背の高い相手と真剣勝負を繰り広げ、70年代には全米的な旋風を巻き起こしました。彼らの試合は単なるスポーツではなく、小人症への理解を広めるためのパフォーマンスでもありました。
報われぬ功績への賛辞
本作のキャストには、SFやファンタジー映画の金字塔を支えてきた強者たちが名を連ねています。
デビー・リー・キャリントン(ヴァレリー・ヴォミット役):『ジェダイの帰還』のイウォーク役や『トータル・リコール』のサムリーナ役などで知られ、スタント俳優の権利向上のために声を上げ続けた活動家でもありました。
ケビン・トンプソン(アリ・ゲーター役):『ブレードランナー』や『ジェダイの帰還』に出演したベテランです。
アルトゥーロ・ギル(ウィンディ・ウィンストン役):元DJという経歴を持ち、『スペースボール』など多くの作品で活躍しました。
フィル・フォンダカーロ(グリーザー・グレッグ役):『ウィロー』や『サブリナ』などに出演し、本作ではキャラクターの「声」まで担当した数少ない一人です。
これほど過酷で報われない仕事であったにもかかわらず、彼らは映画に不可欠な役割を果たしました。もし彼らが、あの不快で窒息しそうな衣装を着て、熱中症の寸前まで耐え抜く覚悟を持っていなければ、この映画自体が存在しなかったでしょう。
彼らが多くの映画に残してきた多大な貢献に対して、私たちが払ってきた敬意は、あまりに少なすぎると言わざるを得ません。
グロテスクの肯定
1868年、ロートレアモン伯爵による過激で背徳的な小説『マルドロールの歌』が刊行された。それから約120年後の1987年、ロッド・アマテウ監督による『ガベージ・パイル・キッズ』が世界に放たれた。一見すると接点のない二つの作品だが、芸術として共通しているのは、不潔、タブー、無作法、暴力、そして「悪」とされる側面を、歓喜と共に受け入れている点にある。
ロートレアモンは、人体やその変容を詩的な文章で執拗に描き出した。同様に、ガベージ・パイル・キッズもまた、鼻水Beauty and health care products require approval from relevant units before they can be purchased and imported, so we cannot assist in purchasing them. 、放屁、放尿、嘔吐といった過剰な身体機能に「呪われ(あるいは祝福され)」ている。彼らは、一般的な生理的期待から外れたグロテスクな存在であり、社会が隠そうとする道徳的・肉体的な「醜さ」を体現している。しかし、これらの望ましくないとされる特性を賛美することを通じて、作品は残酷で偽善的な世界に対する批判を展開し、醜いとされるものを「善」として再定義しているのだ。
資本主義という真の醜さ
監督のアマテウにとって、映画を突き動かす真の醜さとは、外見の不潔さではなく「偏見」や「資本主義の食物連鎖」であった。本作は、利益によって動かされる剥き出しの搾取のプロセスをドラマ化している。
ヒロインのタンジェリンは、主人公ドジャーの優しさや魅力に惹かれるのではなく、彼(と彼が使役するキッズたち)をいかに自分の利益のために利用できるか、という点のみに価値を見出す。これは資本主義的な機会主義と搾取の明確な寓話である。劇中、キッズたちがタンジェリンの要求に応えるために「組合スウェットショップ(搾取工場)」という看板の場所から資材を盗み出すシーンがあるが、これは偶然の演出ではない。
物語が進むにつれ、観客は「一般的な美しさ」の陰に潜む抑圧と搾取に気づかされる。ドジャーがタンジェリンの裏切りを知った際、「君のことがもう綺麗だとは思えない」と告げる場面は、本作で最も痛烈な瞬間だ。ドジャーを惹きつけた規範的な美しさは、結局のところ、真の醜さを隠すための仮面でしかなかったのである。
魔法を保つ「謎」の力
本作の舞台となるマンジーニ船長の骨董品店は、歴史と魔法、そして想像力の宝庫である。一方で、利益のみを追求する者たちの目には、そこにあるものはただの価値のないガラクタに映る。アンソニー・ニューリー演じるマンジーニ船長は、異端者たちの守護者であり、世俗の狂気から逃れてきた賢者として描かれている。
ガベージ・パイル・キッズはどこから来たのか、なぜバケツに閉じ込められていたのか、彼らが探している仲間とは誰なのか。これらの問いに映画は答えない。しかし、この説明の欠如こそが、本作を洗練されたファンタジーにしている。過剰な設定で窒息させることなく、想像力の余白を残すことで、キッズたちは映画が終わった後も、四輪バギーに乗って夜の闇へと、新たな冒険を求めて走り去っていくことができるのだ。
『ガベージ・パイル・キッズ』は、洗練された映画芸術である。なぜなら、何を残し、何を語らずに置くべきかを、この作品は熟知しているからである。
『ガーベッジ・パイル・キッズ』には、本質的な「怒り」が宿っている。何かに愛想を尽かし、うんざりし、そして何より「観客であるお前たち」を忌み嫌っている。それは単なる不敬というよりは、剥き出しの敵意に近い。パンク・ロックよりも洗練されておらず、パンクが持つ「荒削りで、無作法で、文明化されていない反逆」のエートスを丸ごと共有している。ここには洗練など微塵もない。「醜さ」こそが核心なのだ。これは、文字通り呪われた映画(フィルム・モーディ)であり、観客を批判し、その作品を享受する観客のありようを告発するために設計されている。
本作は、ダダやパンク・ロックに通じる最も大胆な社会批評であり、たとえすぐには理解されずとも、必然的に観客を見出すことになるだろう。その前提を受け入れるならば、ルイス・ブニュエルの『黄金時代』や、トム・グリーンの『フレディの糞どろ棒』とも比肩しうる。これらは、観客の中に嫌悪や絶望、うろたえを引き起こすために作られた「実体」のある表現なのだ。映画は、観客が自分自身の姿を作品の中に見出し、その認識に自己嫌悪を抱くことを求めている。
公開から40年近くが経った今、『ガーベッジ・パイル・キッズ』は、その自己嫌悪を、混迷とした陶酔的なノスタルジーで包み込んでいる。私はこの映画の中に自分を見ている。昔からずっとそうだった。ヒーローたちがすべてにおいて絶対的に正しく、それでいて、好きになることなど到底できず、卑劣なほどに幼稚な映画をどう解釈すべきだろうか。
私は、本作の3年前に公開されたジェフ・カニューの『リベンジ・オブ・ザ・ナード』(1984)のことをよく考える。あれは社会からはみ出したガリ勉たちが、画一的な社会や支配階級に立ち向かう物語だが、最終的に彼らは権力の誘惑に負け、それを乱用してしまう。『ナード』の観客を喜ばせる「ハッピーエンド」は、実のところ、最も好感の持てるヒーローによるレイプによって成り立っていることを忘れてはならない。だが、ガーベッジ・パイル・キッズは違う。
彼らはナードたちと同じようにシステムに反旗を翻すが、決して支配階級には同化しない。それどころか、支配的な文化が「自分たちに合わせること」を要求する。ディズニー映画のように、異形(モンスター)が最終的に悪役として処理される子供向け寓話が多い中で、この結末は極めて異例であり、驚くほど進歩的だ。
1987年の夏、本作が公開されたとき、私は14歳だった。あの夏は『ビバリーヒルズ・コップ2』『プレデター』『アンタッチャブル』『フルメタル・ジャケット』、そして『ロボコップ』や『ダーティ・ダンシング』といった名作が目白押しだった。私は家業の手伝いがない日は朝から映画館に籠もり、午前中に『白雪姫』のリバイバルを見て昼寝をし、午後は『追いつめられて』のような成人向けスリラーを見るような日々を過ごしていた。
そんな多様な映画が溢れていた時期にあっても、『ガーベッジ・パイル・キッズ』は異質だった。それは触れられそうなほど生々しく、それでいて「不気味の谷」に居座り続け、観客との歩み寄りを拒絶していた。SFでもホラーでもファンタジーでもなく、観客に一瞬たりとも「これは作り話だ」と忘れさせない、ブレヒト的演劇のようなメタフィクションだった。
本作は、対立するものの統一と闘争、そして「否定の否定(何かが繁栄するために何かが破壊されなければならない)」を描く、弁証法的唯物論の映画である。ブレヒトの演劇が「思想の演劇」であったように、この映画もまたそうなのだ。本作は、レーガン政権末期の価値観(物質主義や資本主義)に対する抵抗の証として、再評価されるべきである。『ウォール街』や『アメリカン・サイコ』のような分かりやすい攻撃よりも、よほど破壊的なやり方で「ミー・ジェネレーション」の浅薄さへの解毒剤となっている。
この映画のプロットがトッド・ブラウニングの『フリークス』と同じであり、どちらも批評家や大衆から同様の嫌悪感を抱かれたのは、決して偶然ではない。『フリークス』はホラーではなく、健常者の悪党にはない忠誠心と献身を持つ、身体障害者たちを描いた美しいメロドラマだった。当時の観客が、自身の偏見によって映画の読み解きを完全に歪めてしまった事実は、特筆に値する。
『ガーベッジ・パイル・キッズ』は、その認識の戦いを観客に直接突きつける。「見るに堪えない外見だが、その主張には全面的に同意できるキャラクター」を見せられたとき、あなたはその思想に向き合えるだろうか。それとも、単にコンセプトへの嫌悪感だけを理由に、安易な道(拒絶)を選ぶだろうか。
社会のはみ出し者を「廃棄物」として扱う現代社会において、この映画は預言的な輝きを放ち始めている。劇中に登場する、醜い者や障害者を収容する「不細工州立ホーム」という設定は、表面上は馬鹿げている。しかし、ホームレス、精神疾患を持つ人々、病人、高齢者、障害者に対してますます残酷になっていく今の米国を見れば、それが単なる冗談ではないことがわかる。
本作は、私たちが「最も卑小な人々」を守れなければ、全員を裏切ることになるという真理を証明するための、過激なレトリックなのだ。ニーメラー牧師の警告(「彼らが共産主義者を連れ去ったとき、私は声をあげなかった…」)が、これほど明快に表現された例はない。もし国家が彼らを一斉検挙したとしても、多くの人は声を上げないだろう。なぜなら、彼らは私たちの感性を逆なでするからだ。だが、その次は私たちの番かもしれない。
映画の終盤、悪女タンジェリンが再び主人公ドジャーに取り入ろうとしたとき、ドジャーは切なく、しかし端的にこう告げる。「君のことは、もう綺麗だとは思わない」
また、本作は資本主義の搾取性に対する痛烈な攻撃でもある。タンジェリンはキッズを地下室に閉じ込め、無給で服を作らせるスウェットショップ(搾取工場)を作り上げる。彼女は彼らを人間扱いせず、自分の帝国を築くための道具としか見ていない。一方でキッズたちは、社会からはみ出したバイカーたちと連帯する。彼らもまた、社会の主流から切り離され、居場所を奪われてきた者たちだ。
『ガーベッジ・パイル・キッズ』は、私たちの「寛容さ」の限界を試している。それは、自分たちが経験するすべてが、心地よく、娯楽として設計されているべきだという傲慢な期待を打ち砕く。不快なものを排除するのか、それとも牢獄に閉じ込めるのか。キッズたちはそれぞれ、嘔吐、失禁、ひどいニキビ、口臭、粘液、足フェチといった、社会的に「容認できない」欠陥を抱えている。
結局、映画は「善良な」常識人たちをゴミ箱に放り込むことで幕を閉じる。これを単なる稚拙なドタバタ劇と見ることもできるが、そこには道徳的な怒りが込められている。キッズたちの合言葉は「力を合わせれば、何でもできる」だ。私たちはその滑稽さに失笑するかもしれないが、彼らの行動の本質を見てほしい。そして最後に自問してほしい。あなたが都市で快適に過ごすために、誰が隠され、誰が犠牲になっているのかを。
この映画は、もはや「見世物小屋の鏡」ではなく、未来を映す「水晶玉」として読まれるべき時が来ている。それとも、そう気づいたときには、もう手遅れなのだろうか。
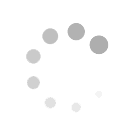


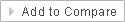
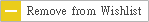
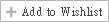














 Malaysia
Malaysia





