ご入札をご検討いただき、誠にありがとうございます。
これは単なる宝飾品ではございません。一つの物語であり、哲学であり、これから人生の荒波に漕ぎ出す、すべての勇敢なる魂に捧げる護符(アミュレット)でございます。
長文となりますが、このジュエリーが宿す本当の価値をご理解いただくため、しばし私の拙い筆にお付き合いいただければ幸いです。
「つまらん。実に、つまらん」
わし、北大路魯山人は、書斎の大きな欅の一枚板の机に肘をつき、庭先に咲き始めた初冬の山茶花(さざんか)を眺めながら、独りごちていた。何がつまらんのか。世の中のすべてだ。昨今、口に入るもの、目に入るもの、手にするもの、そのどれもが、魂の抜け落ちた抜け殻のようだ。料理人は素材の声を聴かず、ただ流行りの調理法をなぞるだけ。陶芸家は土の気性を読まず、ただ奇を衒った形を作るだけ。そして、人間どもは、己の魂を磨くことを忘れ、ただ安楽で、手軽な「相性」とやらを追い求めて、底の浅い関係にうつつを抜かす。
「先生、また難しいお顔をされて。お茶が入りましたが、何か癇に障るものでもございましたか」
そう声をかけてきたのは、わしの身の回りの世話を焼いている、まだ若い書生の木田だ。こいつは多少は骨があるが、やはり現代っ子。物事の本質を見抜くということが、まだまるで分かっておらん。
「木田、お前、結婚とは何だと思う」
わしの唐突な問いに、木田はきょとんとした顔で盆を机の脇に置いた。
「はあ……結婚、でございますか。それは、愛し合う二人が、生涯を共にすると誓い、幸せな家庭を築くことかと」
「ふん、陳腐な答えよ。では聞くが、お前にとって『愛し合う』とはどういうことだ。何をもって『幸せ』とする」
「それは…お互いの価値観が合い、一緒にいて楽しく、安らげること…でしょうか。いわゆる、相性が良い、という…」
「それだ!」
わしは、机をドンと叩いた。湯呑みの茶が、ちゃぷりと揺れる。
「それがいかんのだ!貴様も世間の阿呆どもも、皆、根本的に勘違いしておる。『相性』だと?笑わせるな。結婚相手なぞ、一番相性の悪い奴と結ばれるのが道理なのだ。それこそが、人間がこの世に生を受けてきた意味であり、唯一無二の修行であるということを、何故わからん!」
木田は目を白黒させている。こいつには、まだこの深遠な真理は理解できまい。わしは、ため息をつくと、机の引き出しから、桐の小箱をひとつ、取り出した。古いが、手入れの行き届いた、滑らかな木肌の箱だ。
「これを見ろ」
わしが蓋を開けると、中には黒いビロードの布が敷かれ、その上に、二つの黄金の塊が鎮座していた。鈍く、しかし確かな品格を放つ光。木田が、息を呑んでそれを覗き込む。
「これは…カフス、ですか?なんと美しい…。ゴルフボールの形をしておりますね」
「うむ。ただのカフスではない。エルメスの、18金無垢…いや、正確には中空(ちゅうくう)で仕上げられた逸品だ。F3098という管理番号が、その出自を静かに物語っておる」
わしは、そのうちの一つを、そっと指先でつまみ上げた。ずしり、とまではいかない。11.62グラムという重さが、中空であるが故の軽やかさと、金という素材本来の密度との絶妙な均衡を保ち、指先に心地よい存在感を伝える。直径10.43ミリの球体。その表面には、ゴルフボール特有のディンプル(窪み)が、規則正しく、そして深く刻まれている。
「美しいだろう。このディンプルの一つ一つが、ただの飾りではない。光を受け、あらゆる角度に複雑な陰影を落とす。まるで、それ自体が小宇宙だ。このカフスには、ある女の、そしてわしが先ほど説いた『結婚の真理』のすべてが詰まっておるのだ」
木田は、唾を飲み込み、わしの次の言葉を待っている。よし、この若造に、本物とは何か、人生とは何かを、この一対のカフスを通して教えてやろう。
◇
話は、さるお嬢さんのことから始まる。彼女は、親の代からの資産家の娘で、何不自由なく育った。そして、いつの頃からか、エルメスというメゾン(工房)に取り憑かれていた。世間の女たちが、バーキンだのケリーだのと、ただ記号としてのバッグを欲しがるのとは訳が違う。彼女は、エルメスの真髄、その魂に魅入られていたのだ。
エルメスとは、元来、馬具工房だ。猛々しく、予測不能な力を持つ「馬」という生き物を、人間が制御するための道具。それは、単に美しければ良いというものではない。革の選定、なめし、裁断、縫製、金具の鋳造に至るまで、すべてが一分の隙もなく、機能的かつ堅牢でなければならなかった。鞍が壊れれば、乗り手の命が危うい。手綱が切れれば、暴走を止められない。美は、その極限の機能性と信頼性の先に、副産物として香り立つように生まれるもの。彼女は、そのエルメスの「用の美」の哲学を、生まれながらの感性で理解していたのだ。
彼女の持ち物は、スカーフ一枚、手袋一双に至るまで、すべてがエルメスだった。だが、それはブランドロゴをひけらかすためではない。彼女にとって、それは日常を共にする「道具」として、最も信頼できる相棒であったからだ。彼女の生き方そのものが、エルメスの哲学と共鳴していた。妥協を許さず、本質を求め、自らの基準で物を選ぶ。それ故に、彼女は周りから見れば、非常に気難しく、我の強い、相性の悪い女だったに違いない。
そんな彼女が、ある男と婚約した。男は、新進気鋭の建築家。これまた、自らの美学に絶対の自信を持ち、クライアントの意向なぞお構いなしに、己の信じる空間を創造することに命を懸けるような、偏屈で、頑固な男だった。傍から見れば、水と油。いつ大喧嘩が始まってもおかしくないような二人だった。案の定、彼らの会話は、常に火花が散っていたという。好きな音楽も、好みの食事も、休日の過ごし方も、何一つ合わなかった。
だが、彼らは惹かれ合った。なぜか。互いの内に、己と同じ「妥協なき魂」の輝きを見たからだ。己の信じる美のために、世間と、そして自分自身と戦い続ける孤独な精神。彼らは、表面的な「相性」などという薄っぺらなものではなく、もっと深い、魂のレベルで互いを認め合っていたのだ。
男は彼女に、婚約指輪を贈った。それは、彼自身がデザインした、プラチナの腕に、ただ一粒、しかし完璧なカットのダイヤモンドが埋め込まれた、華美を削ぎ落とした指輪だった。建築家らしい、構造的な美しさを持つ、まさに彼自身を体現したような指輪だった。
さて、問題は、彼女から男への「お返し」だ。時計か、万年筆か。ありきたりのものでは、あの偏屈な男は満足しまい。何より、彼女自身の美学がそれを許さない。彼女は、来る日も来る日も、エルメスのブティックを訪れ、考えあぐねていたという。そしてある日、彼女は、店の片隅のショーケースに置かれた、この一対のカフスを見つけたのだ。
一目見て、彼女は「これだ」と直感した。
なぜ、ゴルフボールなのか。ゴルフというスポーツは、一見、優雅な紳士の遊びに見える。だが、その本質は、孤独な自己との対峙だ。広大な自然という、コントロール不能な舞台の上で、たった一人、己の精神力と技術だけを頼りに、小さなボールを、さらに小さな穴へと導く。風、傾斜、池、バンカー。すべてが障害物だ。そして何より、最大の敵は、己の心の中にいる。焦り、慢心、恐怖。それらに打ち克ち、平常心を保ち続けた者だけが、勝利を手にできる。
このカフスは、まさに、あの建築家の男の生き様そのものではないか。そして、これから始まるであろう、自分たちの結婚生活の象徴ではないか。
木田、よく見ろ。このカフスの構造を。二つのボールが、J字に曲がったバーで繋がれている。これは、離れることのできない二つの魂だ。しかし、同じ方向を向いてはいない。それぞれが独立した球体として、己の存在を主張している。このバーの絶妙な曲線が、二つの魂の間に「距離」と「関係性」を生み出しているのだ。べったりとくっついているのではない。かといって、遠すぎるわけでもない。互いの存在を認め、しかし、決して混じり合うことなく、緊張感を保ちながら共存する。これこそが、理想の夫婦の形ではないか。
そして、この素材。18金。純金(24金)では、柔らかすぎて実用に耐えん。銀や銅を混ぜることで、初めて宝飾品としての強度が生まれる。つまり、純粋なだけではダメなのだ。異質なものが混じり合うことで、より強く、美しい存在へと昇華される。結婚も同じだ。自分と全く同じ人間なぞと一緒になったとて、何の成長も発見もあるまい。自分とは全く違う、異質な価値観、異質な考え方を持つ相手という「合金」が加わるからこそ、己の魂は鍛えられ、摩耗し、より硬く、より輝きを増すのだ。金剛不壊(こんごうふえ)――金剛石のように硬く、決して壊れることのないもの。それこそ、異質なもの同士がぶつかり合い、磨き合うことでしか到達できない境地なのだ。
さらに言えば、この「中空」という作り。これもまた、深い。無垢の金塊であれば、ただ重いだけで、野暮の骨頂だ。これを、中を空洞にすることで、見た目のボリューム感を保ちながら、11.62グラムという軽快さを実現している。これには、極めて高度な職人技が要求される。下手に作れば、すぐにへこむ、歪む。薄く、軽く、しかし、決して壊れない強さ。まるで、熟練の陶芸家が轆(ろくろ)で引き上げた、薄作りの茶碗のようだ。内に大きな空間(包容力)を秘めながら、その輪郭は凛として、揺るぎない。見せかけの重さや権威ではなく、内に秘めた空間と、それを支える技術こそが、本物の価値を生む。
家庭というものも、そうあるべきだ。息が詰まるようなルールや束縛で満たすのではなく、互いの自由な精神が遊べる「空間」がなければならん。しかし、その家庭という器そのものは、幾多の嵐にも耐えうる、確かな信頼と絆によって形作られていなければならない。このカフスは、そのすべてを語っている。
彼女は、このカフスを男に贈った。箱を開けた男は、最初、ただの洒落たカフスだと思ったらしい。だが、彼女が、静かに、しかし熱のこもった声で、なぜこれを選んだのかを語り始めた時、男の顔色が変わった。
「あなたと私の関係は、このカフスのようだ」と彼女は言った。「私たちは、決して簡単には分かり合えない。いつもぶつかり合い、火花を散らすでしょう。でも、それでいい。その摩擦こそが、私たちを磨き、高めてくれる。ゴルフが、自然や自分との孤独な戦いであるように、私たちもまた、それぞれの孤独を抱えながら、共に人生という名のコースを戦い抜くのです。このディンプルの一つ一つが、私たちが乗り越えるべき困難の象徴。そして、この18金という素材が、異質な私たちが混じり合うことで生まれる、新たな強さの証。この中空の構造が、互いを束縛せず、尊重し合う、私たちの関係そのものよ」
男は、黙ってカフスを手に取り、その重さと冷たさと、ディンプルの感触を確かめていた。そして、ふっと笑うと、こう言ったそうだ。
「…まいったな。俺が百年かかって設計図を引くような人生の構造を、君は一瞬で見抜いてしまうのか。これ以上のプロポーズはない」
そうして彼らは結婚した。
◇
「……というわけだ。木田、わかったか」
わしは話を終え、カフスをそっと桐箱に戻した。木田は、呆然とした表情で、まだカフスのあった空間を見つめている。
「先生…。一つのカフスに、そんな物語と哲学が…」
「物とは、そういうものだ。作り手の魂、選び手の見識、贈り手の想い。それらが幾重にも重なり合って、物は初めて『本物』になる。ただの金の塊が、人生の羅針盤にまでなるのだ。それに比べて、現代はどうだ。『相性がいいから』『楽だから』と、安易に相手を選ぶ。それは、己の魂を磨くための砥石(といし)を、自ら放棄するに等しい愚行だ。相性の悪い相手と暮らすことこそが、修行なのだ。相手の理不尽さに耐え、己の未熟さを知り、妥協点を探り、時には激しくぶつかり、それでもなお、共に歩むことをやめない。その苦しみと骨折りの果てにしか、人間的な成長はない。食い物もそうだ。苦味、渋み、えぐみ。そうした『不快』な味を乗り越え、その奥にある旨味を理解してこそ、食通への道は開ける。甘くて美味いだけのものなぞ、子供の食い物だ」
結婚とは、人生で最も長く、そして過酷な修行の場だ。そこで手を取り合う相手は、自分にとって最も扱いにくく、最も理解しがたい、一番相性の悪い人間でなければならん。その相手を、生涯をかけて理解しようと努めること。その過程で、自分自身が変容し、成長していくこと。それこそが、神が、あるいは仏が、我々に課したもうた、この世に生を受けた意味なのだ。
「そのお嬢さんと建築家は、その後どうなったのですか?」
木田が、恐る恐る尋ねた。
「知らん。だが、きっと今も、毎日喧嘩しながら、互いに最高の作品を作り続けていることだろう。彼らにとっての家庭は、安らぎの場ではない。戦場であり、工房であり、道場なのだ。そして、時折、男がこのカフスを身に着けて正装する時、二人は、あの婚約の日の誓いを、言葉なく確認し合うのだろう。我々は、この困難な道を選んだのだ、と。なんと豊かな人生ではないか」
わしは、立ち上がり、書斎の窓を大きく開け放った。冷たい冬の空気が、流れ込んでくる。庭の山茶花が、その寒さの中で、凛として鮮やかな紅色の花びらを開いていた。
「木田、わかったか。相性の悪さこそが、最高の相性なのだ。難しさにこそ、価値がある。このエルメスのカフスが、100年経っても色褪せぬ輝きを放ち続けるのと同じようにな」
わしの言葉が、冬空に吸い込まれていく。若造の心に、この真理のかけらが、少しでも届けばよいが。まあ、わからなければ、それもまた、そいつの人生だ。本物を見抜く目を持たぬ者は、結局、偽物ばかりに囲まれて、薄っぺらい人生を送るだけの話よ。
わしは、桐箱を再び引き出しの奥深くへとしまいながら、一人、満足げに頷いた。このカフスは、やはり、ただの装飾品ではない。人生という名の、最も難解で、最も美しいコースを攻略するための、魂の設計図なのだから。
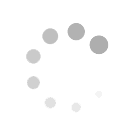




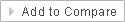
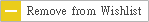
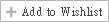







 Malaysia
Malaysia





