以下、所謂ブラクラ妄想ショートショートです〜〜
冬の光(Luce d'Inverno)
序章:静謐なるオブジェ
それは、一つの完成された沈黙だった。
黒いベルベットの上で、18金ホワイトゴールドのネックレスは、まるで自ら発光しているかのような冷たい輝きを放っていた。イタリアの熟練工が丹念に施したであろう、細やかなダイヤモンドカットが施されたビーズチェーン。その一つ一つが、極小のミラーボールのように周囲の光を拾い、そして厳選された角度へと散らしていく。光の粒子が、金属の上で踊っているかのようだ。
長さは42cm。女性のデコルテに寄り添うように設計された、絶妙な長さ。そして、その中心からY字に垂れ下がるデザインが、このネックレスに唯一無二の個性を与えていた。連なるのは、同じくダイヤモンドカットが施された、大小いくつものリング。古代の鎖か、あるいは未来の幾何学模様か。その連なりの終端は、静かに、しかし確固たる存在感を持って胸元に落ちる。総重量21.2g。その重みは、けして所有者を威圧するものではなく、むしろ確かな価値と、それにまつわる記憶の重さを心地よく伝えるためのものだった。
プレートに刻まれた「ITALY」と「750」の刻印。そして、このジュエリーが日本の地に渡るきっかけとなった、スイスの一流商社の名。それは品質と来歴の証。しかし、このネックレスがこれから紡ぎ出す物語は、そんなスペックシートでは到底語り尽くせない、人間の感情の深淵へと続いていく。
人々はそれをただの装飾品と呼ぶかもしれない。だが、それは違う。これは記憶の器であり、言葉にならない想いの媒介者であり、そして、三代にわたる女性たちの魂の軌跡を繋ぐ、一条の光そのものだった。
人々はこのネックレスを、その輝きから「Luce d'Inverno」――冬の光、と呼んだ。
第一章:絹枝の選択
昭和の終わりが近づき、世の中が浮かれた好景気に沸いていた頃。齋藤絹枝(さいとう きぬえ)は、夫の海外赴任に伴い、スイスのジュネーブで暮らしていた。彼女は、絵に描いたような駐在員の妻ではなかった。華やかなパーティや社交界にはあまり顔を出さず、一人で美術館を巡り、レマン湖のほとりを散策し、古書店で埃をかぶった画集をめくることを好んだ。
彼女の内には、誰にも明かしたことのない、静かでしかし燃えるような情熱の炎があった。若い頃、彼女は画家を志していた。だが、厳格な父の反対と、時代の空気の中で、その夢はいつしか心の奥底にしまい込まれ、固く蓋をされていた。良家の男と見合い結婚をし、娘を産み、貞淑な妻として、優しい母として生きること。それが彼女に与えられた役割だった。
娘の怜子(れいこ)は、絹枝に似ず、理知的で、感情をあまり表に出さない子供だった。絹枝が絵筆を握ろうとすると、怜子は「お母様は、お母様でいてください」と、子供らしからぬ冷静な声で言った。その言葉は、絹枝の心に小さな棘のように刺さった。怜子にとって、母は「母」という役割以外の何者でもあってはならなかったのだ。絹枝は、娘を愛していた。愛しているからこそ、彼女の望む「完璧な母」であろうと努めた。そして、その努力は、彼女自身の心を少しずつ蝕んでいった。
ジュネーブでの生活も五年が過ぎたある日、絹枝は夫から一枚の招待状を渡された。夫が懇意にしているスイスの商社が主催する、プライベートな宝飾品の展示販売会だった。夫は言った。「何か一つ、好きなものを選ぶといい。いつも苦労をかけているから」
その言葉に、絹枝は素直に喜べなかった。それはまるで、彼女の我慢と沈黙に対する対価のように聞こえた。しかし、彼女は穏やかに微笑んで頷いた。
会場は、ジュネーブの旧市街にある、石造りの重厚な建物だった。選ばれた顧客だけが招かれるその空間は、静かな興奮と、宝石の放つ目に見えないほどのエネルギーで満たされていた。ルビーの燃えるような赤、サファイアの深く澄んだ青、エメラルドの生命力あふれる緑。絹枝は、それらの宝石には目もくれず、会場の隅にある、ひっそりとしたホワイトゴールドのコレクションへと引き寄せられた。
そして、彼女はそれを見つけたのだ。「Luce d'Inverno」。
派手さはない。だが、その静謐な輝きは、絹枝の心の奥深くに直接語りかけてくるようだった。ダイヤモンドカットのリングが連なる様は、まるで固く閉ざされたいくつもの扉のようにも、あるいは、決して交わることのない運命の輪のようにも見えた。それは、絹枝自身の人生のメタファー※Please confirm whether it is animal fur. Animal fur products are in conflict with the Washington Treaty and cannot be shipped internationally. のようだった。
「こちらでございますか、マダム」
商社の担当者が、丁重に話しかけてきた。
「はい。これを、見せていただけますか」
絹枝がベルベットのトレイに載せられたネックレスを指さすと、担当者は白い手袋をした手でそっとそれを持ち上げた。
「これは、イタリアの工房で特別に作られた一点物でございます。デザインは『連鎖する魂』。過去から未来へ、母から娘へと受け継がれていく想いを表現している、とデザイナーは語っておりました」
母から、娘へ。その言葉が、絹枝の胸を突いた。怜子。感情を表に出さず、母に完璧さだけを求める娘。このネックレスは、いつか怜子の胸元で輝くのだろうか。いや、今の怜子には、この静かな輝きの意味はわかるまい。
これは、誰かのためではない。夫への感謝でも、娘への遺産でもない。これは、私のためのものだ。画家になる夢を諦め、妻として、母として生きてきた「齋藤絹枝」という一人の女性が、自分自身のためだけに選ぶ、初めての宝物。この輝きは、私が私であることを肯定するための光だ。
絹枝は、誰にも聞こえない声で、心の中で呟いた。
「これ、いただきますわ」
その決断は、彼女にとって、一枚の絵を完成させることにも等しい、創造的な行為だった。
日本に帰国してからも、絹枝がそのネックレスを身につけることは滅多になかった。それは桐の箪笥の奥深く、彼女の最も大切なものをしまうための小さな引き出しに、静かに眠っていた。時折、一人の夜に、彼女はそっとそれを取り出し、月明かりの下でその輝きを確かめるだけだった。ネックレスは、絹枝だけの秘密の共犯者のように、冷たく、そして優しく彼女の肌に触れた。それは、誰にも侵されない、彼女だけの聖域の証だった。
第二章:怜子の枷
母、絹枝が亡くなったのは、怜子が45歳になった年の冬だった。
怜子は、都心の一等地にオフィスを構える、名の知れた建築設計事務所の代表を務めていた。コンクリートとガラスThe page has a fragile description, and fragile items cannot be shipped by sea. They can only be shipped by air. If the goods are not fragile, they can be shipped by air. で構成された、無駄を一切削ぎ落としたミニマルな建築を得意とし、その仕事ぶりは、彼女自身の生き方をそのまま反映しているかのようだった。感情に流されず、常に論理と効率を重視する。社員からも、クライアントからも、「有能だが、冷たい人」と評されていた。
母の死は、怜子のスケジュールに突然割り込んできた、予定外のタスクでしかなかった。涙は一滴も出なかった。ただ、粛々と葬儀の準備を進め、滞りなく喪主を務め上げた。周囲は、気丈な娘だと噂したが、怜子自身は、何も感じていない自分に戸惑いさえ覚えていた。
母は、いつも完璧だった。完璧な妻、完璧な母。その完璧さが、怜子にとっては息苦しいほどのプレッシャーだった。母のようにはなれない。だから、私は違う道を行く。怜子が建築の世界に身を投じたのは、母という存在からの逃避でもあった。感情や曖昧さを排した、数字と線で構築される世界。そこにこそ、彼女の安息の地があった。
遺品整理をしていた時、妹から「お姉さん、これ、母さんからだって」と、小さな桐の箱を手渡された。中には、古い便箋と、黒いベルベットのケースが入っていた。
便箋には、母の美しい筆跡で、こう書かれていた。
『怜子へ。あなたに、私の「光」を託します。いつか、この光の意味がわかる時が来るまで、大切に持っていてください。 母より』
光?意味がわからない。怜子は眉をひそめながら、ベルベットのケースを開けた。
そこにあったのが、「Luce d'Inverno」だった。
怜子は、そのネックレスを見た瞬間、息を呑んだ。美しい。それは否定できない事実だった。しかし、その美しさは、怜子をひどく苛立たせた。なぜなら、それはあまりにも「母らしい」ものだったからだ。静かで、上品で、控えめでありながら、決して誰にも本心を見せない、あの母そのものだった。
「光を託します」という言葉が、怜子の心を重くした。それはまるで、母が最後まで「完璧な母」を演じ続け、娘に謎めいた課題を残していったかのように思えた。母は、私に何を伝えたかったのか。なぜ、言葉で言ってくれなかったのか。
怜子はネックレスを身につけてみた。42cmのチェーンは、彼女の首にぴったりと沿った。鏡に映る自分を見て、怜子は愕然とした。そこにいたのは、冷徹な建築家・齋藤怜子ではなく、まるで母の亡霊をまとったかのような、見知らぬ女だった。ネックレスの重さが、まるで母の人生そのものの重さのように、ずしりと彼女の鎖骨にのしかかる。
「似合わない…」
呟きと同時に、彼女はネックレスを乱暴に引きちぎるように外し、ケースに戻した。そして、それを自分のクローゼットの、一番奥の引き出しにしまい込んだ。まるで、見たくない記憶に蓋をするかのように。
それから数年。怜子は仕事に没頭した。いくつもの建築物を世に送り出し、数々の賞を受賞した。私生活では、一度結婚したが、数年で破綻していた。元夫は「君は、心までコンクリートでできているようだ」と言い残して去っていった。一人娘の瑞希(みずき)は、芸術家の道を志し、大学卒業後は定職にも就かず、アルバイトをしながら絵を描いている。怜子には、その生き方が理解できなかった。もっと計画的に、堅実に生きるべきだ。そう思うあまり、瑞希との会話はいつも口論になった。
「お母さんみたいにはなりたくないの」
いつか瑞希に言われた言葉が、深く突き刺さっていた。それはかつて、怜子が自身の母、絹枝に対して抱いていた感情と全く同じだった。歴史は繰り返す。その事実が、怜子をさらに孤独にした。
あのネックレスの存在を、怜子は忘れようとしていた。しかし、忘れることはできなかった。それは引き出しの奥で、冷たい光を放ちながら、静かに彼女を待ち続けているかのようだった。母からの、解けない呪いのように。
第三章:瑞希の発見
令和の時代。齋藤瑞希、24歳。彼女は、時代の空気を吸い込みながらも、どこか息苦しさを感じて生きていた。SNSには、成功と自己実現を謳う同世代のきらびやかな投稿が溢れている。それに比べて自分は、何者にもなれていない。フリーのイラストレーターと名乗ってはいるが、依頼される仕事はウェブサイトの小さなカットばかり。本当に描きたいものは、まだキャンバスの上で形になっていなかった。
母である怜子とは、断絶に近い関係だった。母は、瑞希の生き方を「非生産的」だと断じた。母の言う「正しさ」が、瑞希を追い詰めた。だから、実家を出て、都心から少し離れた古いアパートで一人暮らしをしていた。
そんなある日、母から珍しく連絡があった。家のリフォームをするため、古い荷物を整理したいので手伝いに来てほしい、という業務連絡のような口調だった。気が進まなかったが、断る理由も見つからず、週末に実家を訪れた。
久しぶりに足を踏み入れた実家は、母の設計らしく、物が極端に少なく、生活感のない空間だった。母は、瑞希に自分のクローゼットの整理を言いつけた。
「不要なものは、あなたの判断で捨ててちょうだい」
その投げやりな言葉に、瑞希は少しだけ傷ついた。母のクローゼットは、その生き方同様、白、黒、グレーの服が整然と並んでいるだけだった。その一番奥の引き出し。普段は開けることのないその場所から、瑞希は偶然、あの桐の箱を見つけた。
好奇心に駆られて蓋を開ける。中から現れた黒いベルベットのケース。そして、その中身を見た瞬間、瑞希は時間が止まるのを感じた。
「きれい…」
思わず声が漏れた。それは、瑞希が今まで見たどんなジュエリーとも違っていた。ギラギラとした派手さはない。けれど、そのホワイトゴールドの連なりは、まるで冬の澄んだ朝の光をそのまま固めたかのようだった。ダイヤモンドカットのリングの一つ一つが、複雑な陰影を作り出し、静かに、しかし力強くその存在を主張している。
「何、それ」
背後から、母の声がした。振り返ると、怜子が眉間に皺を寄せ、娘の手元を睨みつけていた。
「これ、お母さんの?すごく素敵」
「…祖母様の遺品よ。私には似合わないから、しまっておいただけ」
「おばあちゃんの?」
瑞希は、祖母である絹枝の記憶がほとんどなかった。物心つく前に亡くなっていたからだ。母は、祖母の話をほとんどしなかった。瑞希にとって絹枝は、仏壇に飾られた、穏やかに微笑む白黒写真の中の存在でしかなかった。
「つけてみてもいい?」
「好きにしなさい」
怜子は吐き捨てるように言って、部屋を出て行った。瑞希は、その冷たい態度に胸を痛めながらも、ネックレスを手に取った。ひんやりとした金属の感触。そして、そっと自分の首にかけてみた。
鏡の中の自分を見て、瑞希は驚いた。Tシャツにジーンズというラフな格好にもかかわらず、ネックレスは不思議と馴染んでいた。そして、その輝きは、瑞希の顔色をぱっと明るく見せた。それはまるで、このネックレスが、瑞希に選ばれるのをずっと待っていたかのようだった。
このネックレスは、一体どんな想いで、祖母の元にあったのだろう。そして、なぜ母は、これほど美しいものを憎むような目つきで見るのだろう。
瑞希の心に、一つの強い想いが芽生えた。
「おばあちゃんのことを、知りたい」
ネックレスを外そうとした時、Y字の付け根部分のリングを繋ぐ小さなパーツが、少し緩んでいることに気がついた。これを直してもらおう。そして、その過程で、このネックレスの物語を聞き出せるかもしれない。
それは、瑞希にとって、自分のルーツを探る旅の始まりであり、止まっていた母との関係を動かすための、最初の小さな一歩だった。
第四章:職人の言葉
瑞希はインターネットで、腕の良いジュエリー職人を探した。チェーン店やブランドショップではない。古くからの品を、その背景ごと大切にしてくれるような、個人の工房がいい。そうして見つけたのが、谷中の一角にひっそりと佇む、「アトリエ・颯(そう)」という小さな店だった。
店のドアを開けると、革のエプロンをつけた若い男性が、ルーペを目に当て、黙々と作業をしていた。瑞希の気配に顔を上げた彼は、思ったよりも若く、真剣な眼差しの中に、少年のような好奇心が宿っているように見えた。彼が、職人の高橋颯太(たかはし そうた)だった。
「すみません、修理をお願いしたいんですけど…」
瑞希がおずおずとネックレスを差し出すと、颯太はそれを受け取り、作業台のライトにかざした。
「これは…」
颯太の目が、一瞬にしてプロのそれに変わった。彼はルーペを手に取ると、食い入るようにネックレスを観察し始めた。チェーンの作り、カッティングの精度、リングの連結部分、留め金の刻印。その指先は、まるで壊れ物を扱うように、それでいて確信に満ちた動きでネックレスに触れていく。
「素晴らしい仕事ですね。70年代から80年代にかけての、北イタリアの職人技だ。この『Cresta di Diamante(クレスタ・ディ・ディアマンテ)』と呼ばれるカッティング技術は、非常に手間がかかる。金属の表面に、計算され尽くした角度で細かい溝を連続して彫ることで、まるでダイヤモンドが埋め込まれているかのような輝きを生み出すんです。今はもう、ここまで手の込んだ仕事ができる職人はほとんどいません」
颯太は、興奮を隠せない様子で早口に語った。彼の言葉は、瑞希がこれまで知らなかった、ネックレスの持つ「顔」を次々と明らかにしていった。
「修理は、この連結部分ですね。大丈夫、すぐに直せます。でも…このネックレス、ただのジュエリーじゃない。作られた時の、職人の魂みたいなものが宿ってる。そして、これを持っていた人の時間も、一緒に吸い込んでいる気がする」
瑞希は、颯太の言葉に引き込まれていた。
「祖母の遺品なんです。でも、母はあまり話してくれなくて…。だから、このネックレスのことをもっと知りたくて」
颯太は、顔を上げて瑞希の目をじっと見た。
「ジュエリーは、雄弁ですよ。言葉以上に、多くのことを語ってくれます。このネックレスは、たぶん、すごく強い意志を持った女性が選んだものじゃないかな。見せびらかすためのものじゃない。自分自身の内面と向き合うための、お守りのようなジュエリーだ。この静かな輝きは、そういう人のためのものです」
その言葉は、瑞希の心を射抜いた。お守り。強い意志。それは、母から聞かされることのなかった、祖母・絹枝の、全く知らない側面だった。
「よかったら、修理が終わるまで、ここで見ていきませんか?この子がどんなふうに作られて、どんなふうに修復されるのか。その過程を見ることも、この子を理解する一歩になるかもしれない」
颯太の提案に、瑞希は頷いた。
小さな工房の中で、瑞希は颯太の作業を静かに見守った。繊細な工具を巧みに操り、緩んだパーツを丁寧に元の位置に戻していく。その集中力と、ジュエリーに対する敬意に満ちた手つきを見ているうちに、瑞希は、自分が描きたい絵のテーマが、少しだけ見えてきたような気がした。
それは、形あるものの奥に宿る、目には見えない物語。受け継がれていく、声なき想い。
「はい、できましたよ」
颯太が差し出したネックレスは、まるで生まれたての時のような完璧な姿を取り戻していた。
「ありがとうございます。あの…また、来てもいいですか?もっと、ジュエリーのこと、教えてほしいです」
「ええ、いつでも。この子(ネックレス)も、喜ぶと思いますよ」
颯太は、はにかむように笑った。
アトリエを出た瑞希の足取りは、来た時よりもずっと軽やかだった。ネックレスは、首元で以前よりも確かな輝きを放っているように感じられた。それは、瑞希の心に灯った、小さな希望の光と共鳴しているかのようだった。
第五章:解ける封印
颯太との出会いをきっかけに、瑞希は本格的に祖母・絹枝の足跡を追い始めた。実家の、今は物置になっている祖母の部屋を、母の許可を得て捜索した。古いアルバム、数冊の日記、そして、埃をかぶった木箱。その中に、絹枝が若い頃に描いたスケッチブックが何冊も入っているのを見つけた。
ページをめくるたびに、瑞希は息を呑んだ。そこに描かれていたのは、瑞希が全く知らなかった祖母の姿だった。ジュネーブの街角、レマン湖の静かな水面、アルプスの雄大な山々。その筆致は、繊細でありながら、生命力に満ちていた。彼女は、ただの「貞淑な妻」ではなかった。世界を、自分自身の目で見て、感じ、表現しようとする、一人の芸術家だったのだ。
最後の日記帳。その最終ページに、あのネックレスに関する記述を見つけた。
『ジュネーブの宝飾店で、一つのネックレスに出会う。イタリアの職人が作ったという、ホワイトゴールドの連なり。その輝きは、まるで冬の朝の光のようだった。誰のためでもない、私だけの光。絵筆を置いた私が、唯一、自分のために行った「創造」。怜子には、まだこの光の重さはわからないだろう。だが、いつか。私の血を受け継ぐ誰かが、この静かな輝きの意味を理解してくれる日が来るかもしれない。その時まで、私の魂のかけらは、この「Luce d'Inverno」の中で眠り続けるだろう』
涙が、日記の文字を滲ませた。祖母は、夢を諦めたわけではなかった。その情熱を、形を変えて、このネックレスに封じ込めたのだ。母から娘へ、と商社の人間は言った。しかし、祖母が本当に託したかったのは、家柄や財産ではない。自分らしく生きたいと願う、切なる魂そのものだったのだ。
そして、瑞希は理解した。母・怜子が、なぜこのネックレスを遠ざけていたのかを。
怜子は、無意識のうちに感じ取っていたのだ。ネックレスに込められた、母の本当の姿を。自分が否定し、逃げてきた「芸術家の母」の魂を。怜子にとって、それは母の裏切りであり、自分がなれなかった自由の象徴だった。だから、見るのが辛かったのだ。その輝きは、怜子の心の傷を、容赦なく照らし出す光だったからだ。
瑞希は、スケッチブックと日記帳を抱え、母の仕事場である設計事務所へと向かった。アポイントもなしに訪れた娘の姿に、怜子は露骨に迷惑そうな顔をした。
「仕事中よ。大事な話でなければ、後にして」
「大事な話だから、来たの」
瑞希は、応接室の大きなテーブルの上に、スケッチブックと日記帳を広げた。そして、自分の首にかけた「Luce d'Inverno」を指さした。
「おばあちゃんは、お母さんが思っているような人じゃなかった。私たちと同じだった。夢があって、悩みがあって、それでも自分らしく生きたいと、必死にもがいていた一人の女性だったんだよ」
瑞希は、日記の最後の一節を、震える声で読み上げた。
怜子は、無言でスケッチブックのページをめくっていた。その指先が、微かに震えているのを、瑞希は見逃さなかった。コンクリートの壁のように固く閉ざされていた怜子の表情が、少しずつ、崩れていく。
「お母さんは、このネックレスが怖かったんでしょ。おばあちゃんの、お母さんが知らない一面を見るのが。自分がずっと逃げてきたものを見せつけられるのが」
「…うるさい」
怜子の声は、かろうじて絞り出されたようだった。
「私は…母のようにはなれないと思った。あの完璧な母には。だから、違う道を選んだ。感情を殺して、仕事に生きてきた。それが、私の強さだと思っていた。でも…違った。私はただ、弱かっただけなのよ。母と向き合うことから、そして、自分自身の心と向き合うことから、逃げていただけ…」
怜子の目から、大粒の涙が、ぽろぽろと零れ落ちた。それは、瑞希が生まれて初めて見る、母の涙だった。数十年もの間、心の奥に閉じ込めてきた、悲しみと、後悔と、そして母への愛情が、堰を切ったように溢れ出していた。
瑞希は、そっと母の隣に座り、その肩を抱いた。
「おばあちゃんは、お母さんを縛りたかったんじゃないよ。逆だよ。自由になってほしかったんだ。このネックレスは、呪いじゃなくて、お守りだったんだよ。お母さんと、そして私のための」
怜子は、嗚咽しながら、瑞希の首にかかったネックレスに、そっと触れた。その指先は、かつてのように拒絶するのではなく、まるで愛しいものに触れるかのように、優しかった。
ホワイトゴールドの冷たい感触が、怜子の指に伝わる。それは、長い間失われていた、母・絹枝の温もりそのもののようだった。ダイヤモンドカットのリングが、応接室の窓から差し込む西日を反射して、怜子の濡れた頬に、虹色のかけらを映し出した。
それは、三代にわたる魂が、ようやく和解した瞬間の光だった。
終章:令和の光
それから、一年が過ぎた。
瑞希は、初めての個展を開いた。テーマは「Luce d'Inverno - 受け継がれる光」。会場には、祖母のスケッチにインスピレーションを得た、力強くも優しい色彩の油絵が並んでいた。その中心に飾られたのは、一枚の肖像画。それは、あのネックレスを胸に、穏やかな、しかし確固たる意志を宿した瞳で微笑む、祖母・絹枝の姿だった。瑞希が、残された写真と、母の記憶と、そして自身の想像力で描き上げた、最高の傑作だった。
会場には、多くの人が訪れた。その中には、颯太の姿もあった。彼は、瑞希の絵を食い入るように見つめ、そして、彼女の隣に来て、静かに言った。
「見えたんだね。君にしか見えない、物語が」
瑞希は、はにかんで頷いた。
そして、会場の入り口には、少し離れた場所から、誇らしげに娘の姿を見つめる怜子がいた。彼女の服装は、以前のようなモノトーンではない。柔らかなアイボリーのジャケットを羽織っている。その胸元には、あの日、瑞希から「今度はお母さんが持っていて」と手渡された、「Luce d'Inverno」が、確かな輝きを放っていた。
ネックレスは、もはや怜子にとって、枷でも呪いでもない。それは、母の愛の証であり、自分自身の弱さを乗り越えた証であり、そして、誇るべき娘へと繋がる、希望の光だった。
個展の最終日。瑞希と怜子は、二人で会場の後片付けをしていた。
「お母さん、そのネックレス、すごく似合ってる」
「そう?…ありがとう」
怜子は、少し照れくさそうに微笑んだ。その笑顔は、瑞希が今まで見た中で、一番美しかった。
「このネックレスが、私たちを繋いでくれたのね」
「うん。おばあちゃんが、きっとそうしてくれたんだよ」
二人は、窓の外に広がる令和の空を見上げた。高く、澄み渡った空。
一つのジュエリーが紡いだ、三代にわたる物語。それは、昭和の静かな情熱から、平成の孤独な闘いを経て、令和の新しい希望へと、確かに受け継がれた。
「Luce d'Inverno」――冬の光。
その輝きは、これからも齋藤家の女性たちの胸元で、時代を超えて、静かに、そして力強く、彼女たちの人生を照らし続けていくだろう。それは、単なる18金ホワイトゴールドの塊ではない。愛と、記憶と、そして未来への祈りが込められた、永遠の魂の光なのだから。
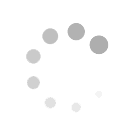



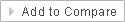
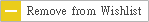
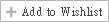






 Malaysia
Malaysia





