すいません。太陽光下で写真追加しようとスタッフに持ってくるように言いましたら見つかりません。泣
来週までには必ず探しておきます!
以下、所謂ブラクラ妄想ショートショートです〜〜
時を超えた十字架の誓い
序章:令和の残響
倉田美咲(くらたみさき)、三十歳。都内のデザイン事務所で働く彼女の日常は、締め切りとクライアントの要求に追われ、灰色のアスファルトのように単調だった。かつて抱いていた創作への情熱は、いつしか生活の重さにすり減り、心は渇いていた。人間関係も、仕事仲間とは表面的な付き合いに終始し、プライベートでは数年前に恋人と別れて以来、心を許せる相手はいなかった。孤独は、静かに、しかし確実に彼女の心を蝕んでいた。
週末、美咲は気分転換にアンティークマーケットを訪れた。雑多な品々が並ぶ中、ある一点に彼女の目は釘付けになる。黒いベルベットの台座に鎮座する、小さな十字架のペンダント。K18の温かみのあるゴールドに、大小さまざまなブラウンダイヤモンドが、まるで古い教会のステンドグラスThe page has a fragile description, and fragile items cannot be shipped by sea. They can only be shipped by air. If the goods are not fragile, they can be shipped by air. のように、静謐な光を放っていた。それは「コニャックカラー」と呼ばれる、深く、芳醇な色合い。中央には、ひときわ透明なダイヤモンドが一石、澄んだ輝きを湛えている。添えられた鑑別書には「天然ダイヤモンド 1.15ct」と記されていた。
何かに導かれるように、美咲はそのペンダントを手に入れた。ラボで人工的に作られたものではない、地球の奥深くで悠久の時を経て生まれた本物の輝き。その重みと、肌に吸い付くような冷たさが、不思議と心を落ち着かせた。帰宅した彼女は、シャワーを浴び、簡素な夕食を済ませると、ベッドの上で改めてペンダントを眺めた。指先でなぞると、ダイヤモンドのファセットが繊細な凹凸を伝え、裏面に刻まれた微かな傷が、その来し方を物語っているかのようだった。
「どんな人が、これを着けていたんだろう…」
そんなことを思った瞬間、眩い光が部屋を包んだ。いや、光ではない。意識が、魂が、どこかへ強く引っぱられるような感覚。目の前が真っ白になり、身体の感覚が消えていく。次に目を開けた時、彼女は自室のベッドではなく、硬く冷たい石畳の上に倒れていた。
第一章:十三世紀のフィレンツェ
むせ返るような革の匂いと、家畜の糞尿の悪臭。人々の怒声と、教会の鐘の音が混じり合う喧騒。美咲が呆然と顔を上げると、そこは見たこともない石造りの街並みだった。薄汚れた衣服をまとった人々が、訝しげな目で彼女を見ている。その服装、髪型、街の様子は、明らかに現代のものではなかった。
混乱する美咲の前に、一人の青年が駆け寄ってきた。
「おい、大丈夫か?こんなところで倒れているなんて。それに、その格好は…」
青年は、麻の質素なチュニックを着て、腰には革の鞄を下げていた。歳の頃は二十代半ば。彫りの深い顔立ちに、太陽のように明るい金色の髪と、憂いを帯びた青い瞳が印象的だった。
「ここは…どこですか?」
かろうじて絞り出した声は、自分のものではないように震えていた。
「どこって…フィレンツェに決まっているだろう。グエルフィ党の連中が見たら、スパイと間違われるぞ」
フィレンツェ。グエルフィ党。歴史の授業で習った言葉が、青年の口から飛び出す。十三世紀、神聖ローマ皇帝派(ギベリーニ)とローマ教皇派(グエルフィ)が激しく対立していた、あの動乱の時代のフィレンツェ。
青年はアレッサンドロと名乗った。彼は、ギベリーニ派の貴族の末裔で、今は没落し、革細工職人として細々と暮らしているという。彼は、奇妙な身なりの美咲を放っておけず、自分の仕事場兼住居である小さなアトリエに匿ってくれた。
美咲は、自分がタイムスリップしたという非現実的な状況を、すぐには受け入れられなかった。しかし、アレッサンドロが灯すランプの揺れる炎も、壁に掛けられたなめし革の生々しい感触も、窓から聞こえるラテン語の祈りの声も、すべてが否定しようのない現実だった。
彼女の胸には、あのコニャックダイヤモンドの十字架が、変わらず輝いていた。アレッサンドロは、その十字架を見て息をのんだ。
「それは…素晴らしい細工だ。まるで、夜明けの光を閉じ込めたようだ」
彼の青い瞳が、十字架の輝きに魅入られている。美咲は、このペンダントが自分をこの時代に連れてきたのだと、直感的に悟った。
第二章:交差する運命
アレッサンドロとの奇妙な共同生活が始まった。美咲は、自分が遠い未来から来たと正直に話したが、彼はそれを信じはしなかった。ただ、記憶を失くした哀れな娘だと思い、優しく接してくれた。美咲は、現代の知識がここでは何の役にも立たないことを痛感しながらも、必死にこの時代の生活に適応しようとした。アレッサンドロの仕事を手伝い、質素な豆のスープを分け合い、彼の語るフィレンツェの歴史や人々の暮らしに耳を傾けた。
アレッサンドロには、婚約者がいた。グエルフィ党に属する豪商の娘、ビアンカ。政略結婚であり、二人の間に愛はなかった。ビアンカは美しく、気位の高い娘だったが、その瞳の奥には深い孤独の色が浮かんでいた。彼女は、ギベリーニの血を引くアレッサンドロを蔑みながらも、彼の持つ気高さと芸術的な才能に、密かに惹かれていた。
ある日、美咲がアレッサンドロのアトリエで革を縫っていると、ビアンカが訪ねてきた。彼女は、美咲の胸に輝く十字架を見つけると、顔色を変えた。
「その十字架…どこで手に入れたのです?」
ビアンカの鋭い問いに、美咲は言葉に詰まる。
「これは…私の…」
「嘘をおっしゃい!それは、私の家、カヴァルカンティ家に代々伝わるものであったはず。数年前、ギベリーニとの争いで屋敷が襲撃された際に、紛失したものよ!」
ビアンカの言葉に、美咲もアレッサンドロも驚愕した。この十字架は、もともとビアンカの一族のものだったというのか。ではなぜ、八百年後の未来で、美咲が手にすることになったのか。
ビアンカは、十字架を返せと激しく詰め寄った。しかし、美咲にとって、それは元の時代に帰るための唯一の手がかりかもしれなかった。返すわけにはいかない。拒絶する美咲に、ビアンカは憎悪の目を向けた。
「あなたのような得体の知れない女が、アレッサンドロ様をたぶらかしているのね。その十字架も、彼を誘惑するための道具なのでしょう。許さない…絶対に」
この一件から、三人の関係は複雑に絡み合い始める。アレッサンドロは、美咲の持つ不思議な雰囲気と、時折見せる未来を知っているかのような言動に、次第に惹かれていく。彼は、美咲が語る「平和で、誰もが自由に生きられる時代」の話を、夢物語と知りながらも、心から求めていた。
美咲もまた、不器用だが誠実なアレッサンドロに、淡い恋心を抱き始めていた。現代で失っていた、人と深く関わることの温かさを、彼が教えてくれたのだ。
一方、ビアンカは、アレッサンドロの心が自分から離れていくのを感じ、美咲への嫉妬と憎しみを募らせていく。彼女は、十字架を取り戻し、美咲をフィレンツェから追い出すため、父親である豪商に偽りの告げ口をした。
「あの女はギベリーニのスパイです。その証拠に、我が家の家宝であった十字架を盗み出し、アレッサンドロ様を内通させようとしています」
第三章:陰謀の渦
ビアンカの父は、娘の言葉を信じ、グエルフィ党の指導者に報告した。ギベリーニの残党を根絶やしにしたい教皇派にとって、それは格好の口実となった。アレッサンドロは、ギベリーニのスパイという濡れ衣を着せられ、捕らえられてしまう。
アトリエに兵士たちが踏み込んできた時の、アレッサンドロの絶望と怒りに満ちた顔が、美咲の脳裏に焼き付いて離れない。彼は、美咲を庇うように兵士の前に立ちはだかり、抵抗むなしく連行されていった。
「私のせいで…私がこの十字架を持っていたから…」
美咲は、自責の念に苛まれた。自分がこの時代に来なければ、アレッサンドロがこんな目に遭うことはなかった。彼を救わなければならない。しかし、何の力も持たない自分に何ができるのか。
途方に暮れる美咲の前に、意外な人物が現れた。ビアンカだった。彼女の顔色は青ざめ、その瞳は恐怖に揺れていた。
「私は…こんなことになるなんて、思っていなかった…。ただ、あなたを追い出したかっただけなのに。父が、党が、アレッサンドロ様を処刑する計画を立てているわ…」
ビアンカは、自分のついた嘘が、愛する人(と、彼女がようやく認めた人)を死に追いやろうとしていることに、耐えられなくなっていたのだ。彼女は、すべてを美咲に打ち明け、土下座して懇願した。
「お願いです。彼を助けてください。私にはもう、何もできない」
敵であったはずのビアンカの涙。その弱さと後悔の念に、美咲の心は揺さぶられた。アレッサンドロを救いたい。その想いは、二人を結びつけた。
二人は、アレッサンドロを救出する計画を立てた。ビアンカは、牢獄の警備兵を買収するための金策に走り、美咲は、アレッサンドロの数少ないギベリーニ派の仲間に助けを求めた。しかし、計画は思うように進まない。処刑の日は、刻一刻と迫っていた。
第四章:十字架の奇跡
処刑前夜。万策尽きた美咲は、アトリエで一人、十字架を握りしめて祈っていた。それは、特定の神への祈りではなかった。ただ、アレッサンドロを救いたい、その一心だった。
「お願い…もし、あなたに力があるのなら…彼を助けて…」
涙が、十字架のダイヤモンドの上に落ちた。その瞬間、八百年前にビアンカの先祖がこの十字架に込めた想いと、美咲の強い願いが共鳴したかのように、ペンダントが熱を帯び、再び眩い光を放った。
――愛する人を、守りたい。その強い想いが、時を超える力を与えるのです――
どこからか、優しく、澄んだ声が聞こえた気がした。
光が収まった時、美咲の手には、一枚の羊皮紙が握られていた。それは、数年前にビアンカの屋敷が襲撃された際、彼女の祖父が隠した手紙だった。そこには、カヴァルカンティ家が密かにギベリーニ派の貴族を匿い、彼らの逃亡を助けていたという衝撃の事実が、詳細に記されていた。そして、その証として、このコニャックダイヤモンドの十字架をギベリーニの亡命者に託した、と。
つまり、カヴァルカンティ家は、グエルフィ党でありながら、党派を超えて人々の命を救おうとしていたのだ。この手紙こそ、アレッサンドロの無実を証明し、同時にグエルフィ党の過激な行動を抑制できる、唯一の切り札だった。
美咲とビアンカは、夜明けと共に、この手紙を携えてグエルフィ党の穏健派の元へと走った。ビアンカは、自らの家の名誉と引き換えに、真実を語った。父の嘘を暴き、アレッサンドロの無実を涙ながらに訴えた。
彼女の勇気ある告白と、動かぬ証拠である手紙を前に、事態は大きく動いた。処刑は寸前で中止され、再審議の結果、アレッサンドロは無罪放免となった。
牢から出てきたアレッサンドロは、やつれていたが、その青い瞳は以前よりも強く輝いていた。彼は、まずビアンカの前に進み、その手を取った。
「ビアンカ。君の勇気に感謝する。君は、自分の過ちを認め、私を救ってくれた。君こそ、真に気高い魂の持ち主だ」
ビアンカは、ただ泣きじゃくっていた。
次に、アレッサンドロは美咲に向き合った。彼は、美咲を強く抱きしめた。
「美咲。君が来てくれなければ、私は今頃ここにはいない。君が語ってくれた未来の話を、私は信じる。いつか、人々が憎しみ合うことのない時代が来るということを」
彼の腕の中で、美咲は安堵と、そして言いようのない寂しさを感じていた。この時代での自分の役目は、終わったのかもしれない。
終章:令和の光
アレッサンドロが解放された日の夕暮れ。フィレンツェの街をオレンジ色の光が包む中、美咲の胸の十字架が、三度、光を放ち始めた。別れの時が来たことを、誰もが悟った。
「行かなければ、ならないんだね」
アレッサンドロが、寂しそうに微笑んだ。
「うん…」
美咲は、涙をこらえて頷いた。
「この十字架は、君が持っていてくれ。これは、君のものだ。君の勇気と優しさが、この十字架に新たな意味を与えてくれたのだから」
アレッサンドロは、美咲の首に、そっと十字架をかけた。
ビアンカも、涙を拭いて美咲の手を握った。
「あなたのこと、決して忘れないわ。ありがとう」
二人の間にあったわだかまりは、もうどこにもなかった。
光が強くなる。アレッサンドロの顔が、ビアンカの顔が、愛おしいフィレンツェの街並みが、光の中に溶けていく。
「さよなら、アレッサンドロ…ビアンカ…」
次に目を開けた時、美咲は自室のベッドの上にいた。窓の外は、すっかり朝になっていた。まるで、長い夢を見ていたかのような感覚。しかし、頬には涙の跡が残り、胸には確かに、あの十字架が温もりを帯びて輝いていた。
その日から、美咲の世界は変わった。単調だった日常が、愛おしいものに感じられた。仕事にも、再び情熱を持って取り組めるようになった。デザインに行き詰まった時は、フィレンツェの美しい街並みや、革製品の温かい手触りを思い出した。それは、彼女だけのインスピレーションの源泉となった。
人間関係も変わった。表面的な付き合いを避け、自分の心に正直になった。すると、不思議なことに、心から信頼できる友人が一人、また一人と増えていった。
ある雨上がりの午後、美咲は打ち合わせのために訪れたギャラリーで、一人の男性と出会った。彼は、新進のジュエリーデザイナーで、個展を開いていた。彼の作るジュエリーは、どれも独創的で、石や金属に魂を吹き込むような、力強い優しさがあった。
彼の名は、藤木彰人(ふじきあきと)。驚いたことに、彼はアレッサンドロに瓜二つだった。同じ金色の髪(もちろん染めているのだが)、同じ憂いを帯びた青い瞳(カラーコンタクトだったが)。
「その十字架、とても素敵ですね。コニャックダイヤモンドの色合いが、まるで歴史を物語っているようだ」
彰人が、美咲の胸のペンダントを見て言った。その声も、仕草も、アレッサンドロを彷彿とさせた。
二人が恋に落ちるのに、時間はかからなかった。彰人は、誠実で、不器用で、そして誰よりも美咲のデザインを理解してくれた。美咲もまた、彼の才能と、その奥にある純粋な魂に惹かれた。
ある日、美咲は彰人に、フィレンツェでの不思議な体験を打ち明けた。彼は、突拍子もない話を、笑わずに最後まで真剣に聞いてくれた。
「信じるよ。だって、君のデザインには、そういう、時を超えたような深みがあるから。そして、その十字架は、君を守るために、僕と引き合わせてくれたのかもしれないね」
彰人はそう言って、美咲の手を優しく握った。
令和の空の下、二人は固く結ばれた。美咲の胸には、いつもあの十字架が輝いている。それはもう、過去への扉ではない。アレッサンドロとビアンカが教えてくれた勇気と優しさの証であり、彰人と出会わせてくれた奇跡の証。そして何より、孤独だった自分自身を救い出し、愛と情熱に満ちた未来へと導いてくれた、かけがえのない宝物なのだ。
コニャックカラーのダイヤモンドは、現代の光を浴びて、芳醇な輝きを放ち続けている。それは、数多の想いを吸い込み、時を超えて受け継がれてきた、愛の物語そのものだった。
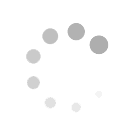





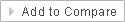
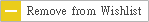
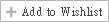








 Malaysia
Malaysia





