序説:南船場地下倶楽部より、選ばれし入札者へ
大阪、南船場。この街の時間の流れは、淀川の水のごとく、表層はせわしなく現代へと向かいながら、その深層には、太閤の時代より続く商人の打算と、明治大正の浪漫、そして昭和の猥雑なエネルギーが、濃厚な澱となって沈殿している。我々の倶楽部が存在するのは、そんな街の、まさに澱の最深部。再開発の波から奇跡的に取り残された、蔦の絡まる煉瓦造りの洋館、その、誰もが存在を知らぬ地下室である。
年に数度、それも、水星が太陽の前面を通過する、稀有な天体の交わりの夜にのみ、我々は重厚なマホガニー※Mahogany trees are items that are in conflict with the Washington Treaty and cannot be shipped internationally. の扉を開く。扉の先には、会員制という言葉すら陳腐に響く、閉ざされた世界が広がる。我々が顧客と認めるのは、単に財を持つ者ではない。富や権力といった、いわば「昼の世界」の価値基準に飽き足らず、モノに宿る物語、人の手が生み出した美に潜む狂気、すなわち「夜の世界」の真価をこそ渇望する、選ばれし魂の持ち主だけだ。故に、我々のコレクションは、その一点一点が、美術館の収蔵品を遥かに凌駕するほどの来歴と、そして「因縁」を纏っている。曰く、王妃の首を飾ったまま断頭台の露と消えた首飾り。曰く、破滅すると知りながらも、代々の所有者が手放すことのできなかった呪いの指輪。我々は、そうした品々に宿る声なき声に耳を澄まし、その物語を、次なる所有者へと語り継ぐことを、至上の使命としているのだ。
今宵、我々は、ヤフーオークションという、ある意味で最も民主的で、最も混沌とした現代の市場に、我々の秘蔵品の中から、極めつけの一品を出品する決断を下した。商品番号「F2603」。我々の間で、畏敬と親しみを込めて『金蜥蜴(きんとかげ)』と呼ぶ、この首飾りである。
一見して、その異様さに目を奪われるであろう。艶を意図的に消された18金無垢の肌は、まるで生きた爬虫類の体温さえ伝えるかのようだ。その蜥蜴が、しなやかな四肢と、力強く巻き付く尾で、必死に抱きかかえているもの。それは、直径17.70ミリという、にわかには信じがたい大きさの南洋黒真珠。ただの黒ではない。光さえ逃げ出すブラックホールのような、絶対的な漆黒。しかし、視線を凝らせば、その深淵から、孔雀の羽を溶かし込んだかのような、妖しい緑や紫の光が、ゆらり、と蜃気楼のように浮かび上がる。蜥蜴の小さな頭頂と、真珠に食い込む尾の先端には、合計0.15カラットの金剛石が、まるで凍てついた星屑のごとく埋め込まれている。
なぜ、我々がこの至宝を、開かれた市場に問うのか。それは、この『金蜥蜴』に込められた物語が、もはや我々だけの地下室に秘匿しておくには、あまりにも濃密で、あまりにも普遍的な、人間の「業」そのものを描き出しているからに他ならない。この物語を理解できる人間は、もはや血統や家柄といった旧来の枠組みの中にはいない。混沌とした現代にこそ、その魂の孤独を、この蜥蜴の姿に重ね合わせることのできる、真の所有者がいるはずだと、我々は信じるのだ。
これから貴方が読むのは、単なる商品説明文ではない。これは、我々の調査員が、古書店に眠っていた一冊の日記、鬼籍に入った関係者たちのかすかな証言、そして大阪という街そのものが記憶する昭和の空気感を、パズルのピースのように組み合わせ、再構成した、一つの長編推理小説である。かの江戸川乱手先生が、もしこの首飾りを手にしていたならば、きっとこのような物語を紡いだに違いない。我々は、先生の霊をこの身に降ろし、代筆者の役割を果たすのみである。
さあ、覚悟はよろしいか。これから貴方は、昭和の闇が生んだ、一人の名もなき宝石職人の、狂おしいまでの愛と妄執の迷宮へと、足を踏み入れることになる。
第一章:蒐集家の独白、あるいは『守宮の翁』を追って
私の稼業を、一言で言い表すのは難しい。世間では、古美術商、あるいは好事家とでも呼ばれるのだろうか。だが、私自身は、自らを「物語の蒐集家」と規定している。特に、人の手によって、その本来の姿を歪められ、屈折した情念を宿すが故に、妖しいまでの美を放つに至った宝飾品に、私は抗いがたい魅力を感じてしまうのだ。私の魂は、完璧な調和よりも、破綻寸前の緊張感の中にこそ、美の真髄を見出すようにできているらしい。これは、一種の呪いであろう。
あれは、平成の世がまだバブルの残り香に酩酊していた頃。私は、大阪の法善寺横丁、その名の通り苔むした不動明王の祠のすぐ脇にある、一軒の怪しげな古物商の暖簾をくぐった。主の老人は、濁った眼の奥に、人の値踏みをするような、それでいてどこか自嘲的な光を宿した、食えない人物であった。私が、何か「曰く」のある宝飾品は無いかと尋ねると、老人は、黄ばんだ歯を見せてにやりと笑い、一つの噂話を語り始めた。
それは、戦前から戦後にかけて、道頓堀の裏筋、いわゆる宗右衛門町の、芸妓たちの置屋が軒を連ねる、迷路のような路地に、神がかった腕を持つ宝石職人がいたという話だった。男は、誰とも交流せず、本名すら誰も知らない。ただ、その工房の軒先に、いつも一匹の大きな守宮(ヤモリ)が張り付いていたことから、界隈の人間は、畏敬と、そして少しばかりの気味悪さを込めて、彼を『守宮の翁』と呼んでいたという。
翁は、顧客からの注文は一切受け付けなかった。彼の創作は、常に、彼自身の内側から、まるで熱病のうわ言のように、噴出する妄想によってのみ、突き動かされた。ひとたび妄想の熱に浮かされると、翁は工房に何ヶ月も籠り、食事も睡眠も忘れたかのように、ただひたすら金槌を振るい、ヤスリを動かし続けた。そして、ある朝、まるで木から果実が熟して落ちるように、工房の小さな窓際に、ぽつりと一つの作品が置かれている。それに気づいた馴染みの仲介人(その古物商の主の、先代であったらしい)が、誰にも見られぬよう、それをそっと懐にしまい、この街の夜の蝶たちを囲う、旦那衆の元へと、秘密裏に届けた。
翁の作品は、その全てが、異様なまでの生命感を宿していたという。特に、蛇、蛙、そして蜥蜴といった、湿り気を帯びた生物をモチーフにしたものが、彼の真骨頂であった。それらは、単なる写実的な彫像ではなかった。まるで、錬金術師がホムンクルスを創り出すように、生きた生物の「精髄」とでも言うべきものを抽出し、金や宝石といった、冷たい無機物の中へと、封じ込めたかのようであったと、老人は、身振り手振りを交え、興奮した口調で語った。
「あれはな、旦那。ただの飾りやない。あれは、呪物(じゅぶつ)ですわ。持つ人間の、心の奥底に隠しとる、一番どろどろした欲望やとか、嫉妬やとかを、喰って生きとるような…そんな品でしたな」
この話を聞いた瞬間、私の蒐集家としての本能が、激しく警鐘を鳴らした。これだ。これこそが、私が生涯をかけて追い求めるべき、究極の「物語」を秘めた宝飾品に違いない。私は、その場で老人に手付金を渡し、『守宮の翁』の作品に関する、あらゆる情報の独占契約を取り付けた。
しかし、そこからの道のりは、困難を極めた。翁の作品は、あまりにも数が少なく、また、その所有者たちは、まるで秘密結社の構成員のように口が固く、決してその存在を明かそうとはしなかった。彼らにとって、翁の作品は、富の象徴である以上に、自身の心の最も暗い部分を映し出す、秘密の鏡のような存在だったのかもしれない。私は、大阪の裏社会に張り巡らされた情報網を駆使し、破産した旧家の蔵漁りから、質屋の横流れ品が集まる闇市まで、考えうる限りの場所を、虱潰しに探し回った。
数年の歳月をかけて、私は、翁の作と思われる数点の品を、幸運にも手に入れることができた。蜘蛛の巣に絡め取られた蝿をモチーフにしたブローチ。自らの尾を喰らう蛇(ウロボロス)をかたどった指輪。それらは、確かに、噂に違わぬ、妖気とでも言うべき気配を放っていた。しかし、私の直感は、これらはまだ、翁の真の最高傑作ではないと告げていた。これらは、来るべき至高の作品を生み出すための、習作、あるいは儀式の生贄に過ぎないのではないか。そんな思いが、私の心を焦燥感で満たしていた。
転機が訪れたのは、全く予期せぬ場所、東京の神保町であった。古書独特の、黴とインクThe ink is liquid and cannot be shipped internationally, please be aware before placing a bid. の匂いが充満する、とある専門書店の片隅。探偵小説や猟奇趣味の雑誌が、天井に届かんばかりに積み上げられた一角で、私は、一冊の古ぼけた大学ノートを、偶然にも見つけ出した。表紙は無地。だが、その紙の焼け具合、インクThe ink is liquid and cannot be shipped internationally, please be aware before placing a bid. の古風な色合いから、昭和初期から中期にかけて書かれたものであることは、疑いようもなかった。
何かに導かれるように、私はそのノートを手に取り、脆くなったページを、そっと捲った。そこに、インクThe ink is liquid and cannot be shipped internationally, please be aware before placing a bid. で書かれた、神経質そうな、それでいて力強い筆跡の文字が、びっしりと並んでいた。それは、ある宝石職人の、創作日誌であった。そして、その中に、私の全身を稲妻のように貫く、一節を発見したのである。
『…江戸川乱歩氏の「パノラマ島綺譚」を、昨夜、三度読み終え、興奮のあまり一睡もできなんだ。かの主人公、人見広介が、孤島を丸ごと一つ、自らの歪んだ美意識のままに、この世ならざる人工の楽園へと変貌させた、あの壮大な狂気! それこそは、芸術家の、いや、神に成り代わらんとする人間の、究極の欲望の姿ではないか。富も、広大な土地も持たぬ、しがない一職人である私に、パノラマ島を建設することなど、夢のまた夢。だが、私には、この両腕と、この指先がある。そして、この脳味噌の中には、広介のそれに勝るとも劣らぬ、醜悪と美が渾然一体となった、妄想の王国が、夜毎、その領土を広げ続けているのだ。ならば、私は、私のパノラマ島を、この掌の上で、宝石という小宇宙の中に、創造して見せよう。地球が億の歳月をかけて生み出した、最も純粋な「自然」の結晶である宝石を、私の歪んだ「人工」の力で、ねじ伏せ、犯し、新たな生命体として、この世に産み落とすのだ…』
人見広介! パノラマ島!
間違いない。この日記の主こそ、私が長年追い求めてきた、幻の職人、『守宮の翁』その人である。私は、震える手で日記を握りしめ、店の主人の怪訝な視線も構わず、その場で読み耽った。
日記は、翁の哲学の、恐るべき深淵を、私に開示してくれた。彼にとって、宝石は単なる輝く石ではなかった。それは「地球の、声なき記憶の断片」。金やプラチナは「人間の、決して満たされることのない欲望の、凝固した姿」。そして、彼がモチーフとする生物たちは「神の気まぐれによって生み出された、束の間の生命を宿す、儚くも愚かしい器」。彼の仕事とは、これら三つの要素を、彼の妄想という名の錬金術の坩堝(るつぼ)の中で、高温で溶かし合わせ、化学反応を起こさせ、永遠と刹那、記憶と欲望、自然と人工が、互いに喰らい合い、交じり合った末に生まれる、全く新しい「完全な生命体」を創造する、神への冒涜にも等しい、魔術的な儀式だったのである。
そして、日記の、まさに最後から二番目のページ。そこには、まるで熱に浮かされたような、乱れきった筆跡で、こう書き殴られていた。
『ああ、ついに、我が至高の作品、我がパノラマ島の中心に据えるべき、暗黒の太陽が、その姿を現さんとしている。蜥蜴だ。古来より、再生と復活の象徴とされてきた、あの卑しくも美しい蜥蜴が、我が漆黒の太陽を、その全身全霊で抱きしめるのだ。あれは、もはや作品ではない。あれは、私の魂そのものなのだ。私が、生涯をかけて焦がれ、そして永遠に失われた、あの人への恋慕であり、届かなかった想いの絶望であり、そして、それでもなお、その記憶と共に生き続けようとする、我が魂の、唯一つの救済なのだ。おお、あれを、いつか手にするであろう、未来の誰かよ。お前は、私の悪夢の全てを、その胸に抱いて、永遠に眠ることになるだろう…』
黒い太陽。蜥蜴。そして、生涯をかけた恋。
この言葉が、私の頭の中で、一つの鮮烈なイメージを結んだ。私は、まだ見ぬその最高傑作の姿を、まるで、生き別れた双子の片割れに再会したかのように、はっきりと、網膜の裏に思い描くことができた。私の探求は、今、その最終章を迎えようとしていた。
第二章:蜥蜴の象徴学と、昭和のレビュー小屋の幻影
翁の日記を手に入れた私は、彼の言う「黒い太陽を抱く蜥蜴」の正体を突き止めるべく、新たな調査を開始した。それは、もはや単なる宝飾品の探索ではない。一人の人間の魂の軌跡を辿る、考古学的な発掘作業にも似ていた。
まず、私は、翁がなぜこれほどまでに「蜥蜴」というモチーフに固執したのか、その理由を探ることから始めた。蜥蜴という生物は、実に多義的な象徴性を、その小さな身体に宿している。
古代エジプトでは、蜥蜴は太陽神ラーの使いであり、毎朝、太陽が東の空に再生するのを助ける、聖なる存在と信じられていた。砂漠の民にとって、太陽の光は、生命そのもの。その再生を司る蜥蜴は、すなわち、死からの復活、永遠の生命の象徴であったのだ。一方、旧約聖書の世界では、蛇と同じく、地面を這い回る不浄な生き物として、悪魔や誘惑の化身と見なされることもある。この、聖と邪、光と闇、再生と堕落という、二つの相反する概念を、平然と同居させている点にこそ、蜥蜴という生き物の、本質的な魅力、あるいは魔性があると言えよう。
日本においても、その両義性は顕著である。家の壁や天井に張り付き、害虫を捕食する守宮(ヤモリ)は、「家守」として、古くから家の守り神、縁起の良い生き物とされてきた。しかしその一方で、ぬらりとした皮膚の質感、素早い動き、そして、じっとこちらを窺うような、感情の読めない黒い瞳は、どこか不気味で、人の心の、じめじめとした暗部を刺激する。井原西鶴の好色物や、上田秋成の雨月物語といった、江戸の文学作品にも、嫉妬や怨念に狂った人間の生霊が、蜥蜴や蛇の姿となって、恋敵の枕元に現れるといった描写は、枚挙に暇がない。愛と憎しみが、同じ一つの感情の、表裏であるように、蜥蜴もまた、幸運と災厄、守護と呪詛の、二つの顔を持っていたのだ。
翁は、この蜥蜴の持つ、二面性に惹かれたのであろうか。いや、それだけではあるまい。日記の記述を読み解くうちに、私は、彼が特に、蜥蜴の持つ、ある特異な生態に、自身の人生を深く投影していたのではないか、という結論に達した。それは、「自切」と「再生」の能力である。
多くの蜥蜴は、敵に襲われた際、自らの意思で、尾の骨を断ち切り、切り離された尾が、しばらくの間、のたうち回ることで、敵の注意をそちらに引きつけ、その隙に本体は逃げ延びる。そして、失われた尾は、不完全な形ではあるが、時間をかけて、再び生えてくるのだ。この、身を切るような痛みを伴う「自己犠牲」と、それでもなお生き延びようとする、健気で、そしてどこか歪んだ「再生」。これほどまでに、我々人間の、心の有り様を、的確に言い表した比喩があるだろうか。
我々は皆、人生の中で、幾度となく、心を切り刻まれるような経験をする。耐え難い苦しみ、忘れたい過去、断ち切りたいと願う人間関係。そんな時、我々は、蜥蜴が尾を切り捨てるように、自らの心の一部を、麻痺させ、切り捨て、見ないふりをすることで、何とか正気を保ち、生き延びようとするではないか。しかし、そうやって失われた心の一部は、決して、元の形では再生しない。それは、歪んだ、不格好な、しかし、それでも生きていくためには必要な、新しい心の一部として、我々の内に、残り続けるのだ。
『守宮の翁』は、自身の作品に、この「再生への切ない祈り」と、それと表裏一体をなす「永遠に癒えることのない喪失の痛み」を、同時に刻み込もうとしたのに違いない。彼が創り出す蜥蜴は、生命の輝かしい賛歌などではない。それは、何かを失い、傷つき、それでもなお、醜く、必死に、生き永らえようとする、我々自身の、痛々しい肖像なのだ。
では、その蜥蜴が抱くという「黒い太陽」とは、一体、何を意味するのか。
その謎を解く鍵は、日記の中に、断片的に記されていた、翁の、若き日の恋愛譚にあった。
時代は、昭和初期。浅草六区が、エロ・グロ・ナンセンスの、猥雑で、しかし、底抜けに明るいエネルギーに満ち溢れていた頃。翁は、まだ見習いの、無口な職人であった。彼は、仕事が終わると、毎晩のように、浅草のレビュー小屋「カジノ・フォーリー」へと通い詰めていた。彼の目当ては、ただ一人。踊り子の、水島すみれ、という娘であった。
日記の中の翁は、彼女の姿を、ほとんど神を崇めるかのような、熱に浮かされた筆致で描写している。スポットライトを浴びて、滑るように舞う、その肢体。汗に濡れた肌は、まるで、月光を溶かし込んだ、最高級の真珠のようであったという。そして、彼女の瞳。それは、他の踊り子たちのような、客に媚を売るような光ではなく、全てを見透かし、そして、その奥に、底知れぬ孤独と哀しみを湛えた、夜の海よりもなお深い、漆黒の色をしていた、と。
翁は、ただの一度も、彼女に声をかけることなどできなかった。彼は、いつも、一番安い、三階の立見席の、最も暗い隅から、まるで、聖母像を拝む、熱心な信者のように、彼女の姿を、ただ、ひたすらに、網膜に焼き付けていた。彼にとって、彼女は、もはや一人の人間ではなく、美そのものの化身であり、彼の、薄暗く、希望のない日常を照らす、唯一つの「太陽」であった。
しかし、ある日、突然、その太陽は、彼の空から、永遠に失われることになる。
水島すみれは、忽然と、レビュー小屋の舞台から、姿を消したのだ。病に倒れたとも、満州に渡った大物の軍人の、囲い者になったとも、様々な噂が飛び交った。翁は、半狂乱になって彼女の行方を探したが、しがない一職人に、知る術など、あろうはずもなかった。
彼の心には、ぽっかりと、巨大な空洞が空いた。太陽を失った世界は、色を失い、ただ、モノクロームの、冷たい闇が、広がっているだけだった。彼は、絶望のあまり、自らの命を絶つことさえ、考えたという。
だが、その時、彼の脳裏に、一つの、狂気的な考えが、閃いた。
そうだ。失われたのならば、私が、もう一度、創り出せば良いのだ。この世で最も硬く、最も美しく、永遠に朽ちることのない物質を用いて、彼女の幻影を、この地上に、永遠に繋ぎ止めてみせよう、と。
彼女の、あの真珠のようだった肌は、最も大粒で、最も深く、そして、最も傷のない、漆黒の南洋真珠で。
彼女の、あの夜の海のような瞳は、真珠の奥底に、ゆらめく、虹色の光(オリエント)で。
そして、彼女という太陽に焦がれ、その周りを、ただ、衛星のように回り続けることしかできなかった、愚かで、哀れで、しかし、一途な、自分自身の魂の姿を、一匹の蜥蜴として、その黒真珠に、永遠に抱きつかせるのだ、と。
蜥蜴は、翁自身。黒真珠は、彼が神格化した、永遠の恋人の、記憶の結晶。
この作品は、もはや、単なる宝飾品ではない。それは、叶わなかった恋の、壮絶なまでの鎮魂歌(レクイエム)であり、翁の魂そのものが、物質化した、一つの聖遺物(レリック)だったのである。
第三章:黒球との邂逅、そして南船場の夜
翁の日記を解読してから、更に十数年という、気の遠くなるような歳月が流れた。私は、もはや『黒球を抱く金蜥蜴』の探索を、半ば諦念と共に、続けていた。翁が、この世を去ってから、久しいであろうことは、想像に難くない。あの最高傑作は、一体、どこで、誰の元に、眠っているのか。あるいは、その真価を誰にも理解されぬまま、無残にも溶かされ、素材として、他の、魂のない宝飾品の一部と成り果ててしまったのではないか。そう考えると、私の胸は、まるで、鋭い錐で、ゆっくりと抉られるかのように、鈍く、そして深く、痛んだ。
そんな、ある秋の日の夕暮れ。私の元に、一本の、旧式の黒電話からの、着信があった。声の主は、私が長年、情報提供を依頼していた、大阪の裏社会に精通する、古美術ブローカーであった。
「先生…長らくお待たせいたしました。…どうやら、お探しの『お化け』が、近々、南船場の、とある『夜会』に、姿を現すようでございます」
その言葉に、私は、全身の血液が、一瞬で沸騰するのを感じた。南船場の、夜会。それは、私が、以前からその存在を噂で聞き、いつかは訪れたいと切望していた、あの、秘密のブランド倶楽部に、違いなかった。
ブローカーの手引きにより、私は、その倶楽部への、一枚の、分厚い和紙に墨で書かれた、招待状を、手に入れることができた。そして、指定された、新月の夜。私は、心斎橋の喧騒を背に、石畳の残る、南船場の古い街並みへと、足を踏み入れた。地図にも載らぬ、その煉瓦造りの洋館は、まるで、周囲の現代的なビルから、ここだけが、昭和の時代に取り残されたかのように、ひっそりと、しかし、圧倒的な存在感を放って、闇の中に、佇んでいた。
地下へと続く、螺旋状の、錆びついた鉄の階段を、一歩、また一歩と、降りていく。自分の心臓の鼓動が、やけに大きく、耳に響いた。重厚な、マホガニー※Mahogany trees are items that are in conflict with the Washington Treaty and cannot be shipped internationally. の扉の前に立つ。意を決して、その扉を、ゆっくりと、押し開けた。
そこは、外界の時間が、完全に遮断された、静寂と、そして、濃密な美意識に満たされた、異次元の空間であった。壁には、深紅の、厚いビロードが張り巡らされ、床には、ペルシャ絨毯が敷き詰められている。琥珀色の、柔らかな間接照明が、部屋の各所に置かれた、アンティークのガラスThe page has a fragile description, and fragile items cannot be shipped by sea. They can only be shipped by air. If the goods are not fragile, they can be shipped by air. ケースを、幻想的に照らし出している。その中には、どれもが、一目で、尋常ならざる来歴を持つとわかる、宝飾品や美術品が、まるで、生きているかのように、静かに、鎮座していた。客は、私一人。部屋の最も奥、清朝時代のものと思われる、螺鈿細工が施された、豪奢な椅子に、一人の老婦人が、背筋を、すっと伸ばして、静かに、座っていた。
銀色に輝く髪を、高く、気品のある形に結い上げ、黒の、シンプルな、しかし、最高級のシルクとわかる、チャイナドレスに、身を包んでいる。その佇まいは、まるで、往年の、サイレント映画の女優のようであった。彼女が、この倶楽部の、主であろう。
「…ようこそ、お越しくださいました。貴方様が、長年、父の作品を、探しておられたことは、聞き及んでおります」
老婦人は、ゆっくりと、私に視線を向けた。その声は、鈴が鳴るように、澄んでいながら、しかし、その奥に、幾多の歳月と、物語を、秘めているであろう、深い響きを持っていた。
父。その一言に、私は、思考が、完全に停止するのを感じた。父? では、この女性は、『守宮の翁』の、娘…?
私の混乱を、見透かしたかのように、老婦人は、その薄い唇の端に、微かな、哀しげな笑みを、浮かべた。
「お察しの通り、父には、生涯をかけて、焦がれた女性が、おりました。浅草の、レビュー小屋の…。ですが、父は、あまりにも、臆病で、不器用な男でございましたから、その想いを、一度として、言葉にすることは、叶いませんでした。…私は、父が、その女性と別れた後、まるで、魂の抜け殻のようになってから、見合いで結婚した母との間に、生まれた娘でございます。父は、母や、私のことを、それなりに、慈しんではくれました。ですが、その魂は、いつも、どこか、遠い場所を、彷徨っているようでした。まるで、この世ならざる、美しい星でも、見上げているかのように…」
彼女は、静かに、椅子から立ち上がった。そして、部屋の最も神聖な場所と思われる、黒檀※Black sandalwood products are in violation of the Washington Treaty and cannot be shipped internationally. でできた、一台の小さな台座の方へと、私を、手招きした。その上には、桐でできた、一つの、古びた箱が、厳かに、置かれていた。
老婦人は、まるで、聖体にでも触れるかのように、敬虔な手つきで、その箱の蓋を、ゆっくりと、開けた。
箱の内側には、真綿が、厚く、敷き詰められていた。
そして、その中央に。
それは、まるで、闇そのものが、凝縮して、生まれたかのような、圧倒的な存在感を放って、鎮座していた。
『黒球を抱く金蜥蜴』。
私は、息を、呑んだ。いや、呼吸そのものを、忘れていた。
それは、私が、長年、夢の中で、何度も、何度も、思い描いてきた姿、そのものであった。いや、違う。私の、貧困な想像力など、まるで、赤子の戯言のように、嘲笑うかのような、神々しくも、冒涜的なまでの、実在感。
艶を消された18金の蜥蜴は、日記の記述通り、まるで、今、この瞬間にも、ぬらり、と動き出しそうな、生々しいまでの質感で、巨大な黒真珠に、しがみついていた。その四肢の指の一本一本、皮膚の微細な皺に至るまで、執拗なまでの写実性で、作り込まれている。その瞳と、真珠に、食い込むように留められた尾の先のダイヤモンドが、部屋の、琥珀色の光を、鋭く、冷たく、反射していた。
そして、何よりも、その黒真珠。直径17.70ミリという、物理的な大きさを超えた、一つの、完結した、小宇宙。覗き込めば、自分の顔が映る。だが、それは、単なる鏡像ではない。その漆黒の奥に、自分の魂が、吸い込まれ、引きずり込まれていくかのような、めまいにも似た、感覚。表面に、ゆらりと浮かび上がる、孔雀の羽色の、妖しい光は、まるで、この黒い球体の内部に、封じ込められた、別の世界の、景色が、映り込んでいるかのようであった。私は、江戸川乱歩の、あの『鏡地獄』の、恐ろしい結末を、思い出していた。この真珠もまた、同じ種類の、人の正気を、静かに、しかし、確実に、蝕んでいく、魔性を、秘めている。
「父は、これを、完成させた、その日の夜。私を、工房に呼びました」
と、老婦人は、遠い過去を、手繰り寄せるように、静かに、語り始めた。
「そして、この首飾りを、私の前に、差し出して、こう、言ったのです。『これはな、ワシの、生涯の、恋だ。そして、ワシ自身の、醜い、執着の、塊だ。この蜥蜴は、ワシだ。決して、手に入れることのできぬ、あの気高い太陽に、焦がれ、嫉妬し、それでも、その周りを、うろつき、しがみつくことしかできん、哀れで、卑しい、生き物の姿だ。だがな、それでも、ワシは、この執着を、手放すことは、できんかった。この蜥蜴の尾は、最後の最後で、この黒い世界に、己の身を、食い込ませておるだろう。ワシの魂は、こうして、永遠に、あの人の記憶と、一体になるのだ』…と」
老婦人の、その美しい目に、一筋の、涙が、光った。
「父は、これを完成させた、数日後。まるで、蝋燭の火が、燃え尽きるように、静かに、息を、引き取りIt is possible that the product can only be picked up by yourself, and the self-pickup fee is quite high, please check the page to confirmました。己の、魂の、その全てを、この、小さな一つの作品に、注ぎ込み、燃やし尽くして、しまったのでございましょう。…父の死後、私は、この首飾りを、誰の目にも触れさせず、この桐の箱に納め、大切に、しまってまいりました。父の、あまりにも、純粋で、そして、あまりにも狂気的な魂が、今も、この中に、生きて、宿っているようで、恐ろしかったのでございます。しかし、もう、私も、このような、歳になりました。このまま、父の魂の物語を、私一人の、秘密として、墓場まで、持っていくことは、父に対して、あまりにも、申し訳がない。そう、思うように、なったのです。この作品に込められた、父の、哀しいまでの物語を、正しく、理解してくださる方の元へ、この魂を、お譲りしたい。そう、ずっと思い続けて、今日まで、参りました」
彼女は、その首飾りを、そっと、手に取った。そして、私の方へと、恭しく、差し出した。
私は、まるで、聖杯でも、受け取るかのように、震える、両の指で、それを受け取った。
ずしり、とした、重み。
17.56グラムという、物理的な質量だけではない。
一人の人間の、一生分の、狂おしいまでの、愛と、孤独と、執念の、その全ての重みが、私の掌に、のしかかってくる、ようであった。
金の蜥蜴の、ひんやりと、そして、どこか、湿り気を帯びたかのような、感触。
黒真珠の、全てを、吸い込んでしまいそうなほどの、滑らかさと、深淵。
私は、その時、確かに、感じた。
この首飾りが、今、この瞬間も、私の掌の上で、静かに、呼吸しているのを。
『守宮の翁』の、満たされることのなかった魂が、今もなお、この金の蜥蜴の中に、宿り続け、永遠に失われた恋人の幻影である、この黒真珠を、抱きしめ、そして、求め続けているのを。
それは、もはや、宝飾品などという、言葉で、分類できる、存在ではなかった。
それは、昭和という、光と闇が、混沌と、猥雑に、入り混じった時代に生きた、一人の、名もなき、しかし、紛れもない天才職人が、江戸川乱歩の、幻想と倒錯の世界に、自らの魂を、深く、共鳴させながら、己の人生の、その全てを、賭して、創り上げた、一つの、立体的な「私小説」であり、永遠に癒えることのない、魂の「傷痕」そのものであった。
結び:この物語の、次なる「共犯者」へ
以上が、商品番号「F2603」、我々が『金蜥蜴』と呼ぶ、この首飾りにまつわる物語の、我々が知り得た、全貌でございます。ノーブルジェムグレイディングラボラトリー発行の鑑別書は、この品が、物理的に、最高級の18金無垢と、極めて希少な17.70ミリの南洋黒真珠、そして、寸分の曇りもない、天然のダイヤモンドから、構成されていることを、冷徹な、科学の目で、証明しております。
しかし、我々、南船場倶楽部が、貴方に、保証するのは、そのような、物質的な価値などでは、決してございません。我々が、我々の全ての名誉をかけて保証するのは、この首飾りが、一人の人間の、狂おしいまでの愛と絶望、そして、芸術への、神をも恐れぬ執念が、奇跡的に、結晶化した、この世に、二つと存在しない、「物語」であるという、その、厳然たる、事実でございます。
この『金蜥蜴』を、貴方の、その胸元に、飾るという行為。それは、ただ、美しい、高価な装飾品を、身につける、という、表層的な行為には、断じて、留まりません。それは、『守宮の翁』の、満たされなかった魂の物語を、その因果の全てを、貴方自身が、引き継ぎ、その物語の、新たな「共犯者」となることを、意味するのです。
この黒真珠を、覗き込むたび、貴方は、昭和のレビュー小屋の、むせ返るような熱気の中で、幻のように舞った、踊り子の面影と、そして、その幻影に、自らの人生の、その全てを、捧げ尽くした、孤独な職人の、丸まった背中を、見ることになるでしょう。
「視線と話題を集める、チャーミングな蜥蜴ちゃんに、大人余裕を感じます」ですって?
我々の、この長々とした物語を、ここまで、読んでくださった、聡明な貴方ならば、もはや、お分かりのはず。それは、あまりにも、無邪気で、そして、あまりにも、的を射ていない、表現であるということを。この首飾りは、他者の視線を集めるための、道具などでは、断じてない。むしろ、逆。これは、所有者自身の魂を、その内側に、深く、深く、引きずり込み、自己との、孤独な対話を、強いるための、呪具(チャーム)なのです。この蜥蜴が、貴方に、もたらすのは、「大人の余裕」などという、安易な安らぎでは、決してありません。それは、むしろ、自らの心の、最も暗い深淵を、覗き込む、スリルと、恐怖と、そして、その先に、微かに見えるであろう、真実の自己と、向き合うための、「覚悟」なのであります。
さあ、決断の時は、参りました。
この、人間の、愛と狂気の、業そのものを、結晶化させたかのような、首飾り。
その、あまりにも、重く、そして、あまりにも、美しい物語の、最後の、所有者となり、その魂の、語り部となる、覚悟が、貴方には、おありで、ございましょうか。
我々は、南船場の、この地下室の、闇の底から、静かに、そして、厳粛に、貴方の、その、魂の応札を、お待ち申し上げております。
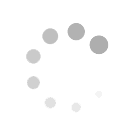



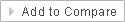
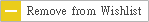
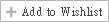








 Malaysia
Malaysia





